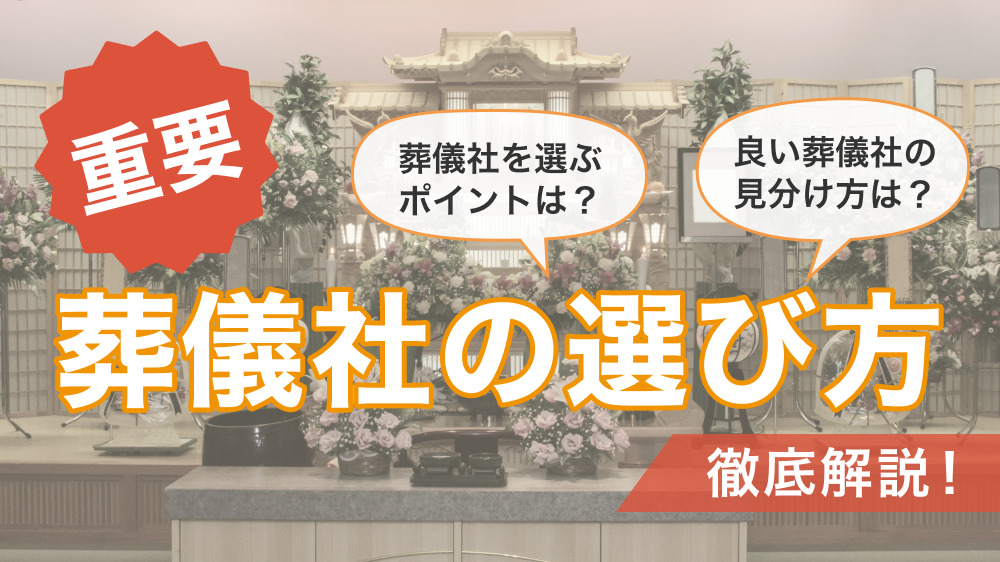お葬式
家族が突然死した場合の対応は?発見した時の注意点や葬儀までの流れをご紹介
更新日:2023.10.16 公開日:2022.08.05

記事のポイントを先取り!
- 検視によって遺体が手元になく葬儀がすぐにできない場合がある
- 突然死の訃報は慌てずに葬儀が決まってから行えばよい
- お墓がない場合は一周忌までに用意するケースが多い
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
【みんなが選んだお葬式】
死因の中でもショックが大きい突然死ですが、その葬儀についてご存じでしょうか。
悲しみの中で冷静な対応ができるよう、葬儀の段取りについて知っておくことが大切です。
そこでこの記事では、突然死の葬儀について解説します。
この機会に、訃報を伝えるタイミングを覚えておきましょう。
後半には、突然死を目撃した際の注意点についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだ終活では365日24時間葬儀に関するお悩みに対応しています。
葬儀にかかる料金などにも回答しますのでぜひお申し付けください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 突然死とは
- 家族の突然死を発見した場合
- 家族が突然死した場合の注意点
- 突然死した家族の葬儀の流れ
- 遺産相続の手続き
- 葬儀日程の決め方
- 【ケース別】亡くなった日時と葬儀日程の決め方
- 葬儀日を決める際の重要なポイント
- 家族が突然死した時の連絡と対応
- お通夜の連絡:適切なタイミングと方法
- お墓はいつまでに用意すれば良い?
- 突然死で亡くなった時のお悔やみの言葉
- 死別の悲しみを乗り越えるための5つの方法
- 家族の突然死についてよくある質問
- 家族が突然死した時のまとめ
突然死とは
突然死とは、不自由なく日常生活を送れる健常者でありながら、特定の要因によって短時間のうちに突然亡くなってしまうことです。
突然死は、WHO(世界保健機構)によって定められた条件が設定されています。
その条件には、高所からの転落や交通事故などが除かれます。
事故を除いた突発的な死亡、もしくは死因となった病気を発症し、24時間以内で死亡した場合が条件とされています。
もし、家族が突然死した場合、家族はどのような対応や葬儀の段取りをすればよいのでしょうか。
家族の突然死を発見した場合

家族が倒れているのを発見し蘇生の可能性がある場合は、すぐに119番に連絡し救急搬送を依頼してください。
しかし、残念ながら蘇生の見込みがなく突然死していた場合は、かかりつけ医がいる場合といない場合で対応方法が変わるため以下でご紹介します。
かかりつけ医がいる場合
故人が生前定期的に通っていたかかりつけ医がいる場合、まずはかかりつけ医に連絡しましょう。
かかりつけ医は、故人の疾患や体質などの記録を持っているため、死因の推察をできることがあります。
死因の判断や死亡診断書の作成など、かかりつけ医はさまざまな要因で適格者とされますので、身内や関係者の方はかかりつけ医に優先的に連絡してください。
かかりつけ医がいない場合
特定のかかりつけ医がいない場合は、ご自宅を管轄している警察署に連絡しましょう。
警察署に連絡することで、警察医と警察官が必要な調査を行います。
死因調査は、事件性及び死因の可能性を特定するために行われます。
調査後、警察からは死体検案書が発行されますので、覚えておきましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
家族が突然死した場合の注意点
家族が突然死した場合、かかりつけ医または警察の到着を待つことになりますが、その時に注意点について以下でご紹介します。
遺体に手を触れない
突然死した家族を発見しても触れたり動かさないように注意してください。
服を着せるなどの行為も死因が判断されるまで行えません。
とくに不審死の場合は警察による検視が必要なため、故意に遺体を動かしたり手を加えることは証拠隠蔽の疑いをかけられる可能性につながってしまいます。
また突然死の原因を確認する上で、すでに亡くなっていることが明らかな遺体を病院へ移送することも、同様の理由で禁止とされています。
死因が不明の場合は警察が引き取る
亡くなった家族の死因が病死や老衰と判断できない場合は警察が引き取り検視を行います。
検視は事件性がなくても、孤独死、自殺、事故死などが対象になります。
検視の結果、事件性がないことが確認されれば「死体検案書」が作成されます。
死体検案書は、死亡からの経過時間や死因が記され、死亡診断書と同じく死亡届などさまざまな書類を申請する際に必要になります。
そのため、死体検案書を複数枚コピーを取っておくことをおすすめします。
警察から死体検案書が作成されたら遺体を引き取り葬儀を行うことが可能になります。
突然死した家族の葬儀の流れ

家族が突然死した場合であっても、老衰と同じように葬儀を執り行い納骨や埋葬が必要です。
ここからは家族が突然死した場合に備え、一般的な葬儀の流れをご紹介します。
納骨についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をお読みください。
死亡診断書(死体検案書)を受け取る
日本において、葬儀には、火葬も一緒に行われるのが一般的です。
そのため、突然死した故人の火葬や埋葬、葬儀に必要な書類は必須になります。
突然死の場合は、医師が発行する死亡診断書、もしくは警察が発行する死体検案書を受け取りましょう。
死亡診断書についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をお読みください。
遺体を引き取り安置する
死体検案書が発行され遺体を引き取れるようになったら、ご遺体の安置場所を決めておかなければなりません。
他の遺族、できれば喪主になりうる人に連絡をして指示を仰ぎましょう。
自分が喪主の立場であるのなら、葬儀社に連絡を取り、安置場所と搬送方法を相談します。
葬儀社には病院・警察の名前、住所・電話番号、そして現在ご遺体のある場所と搬送する時間を伝えます。
信頼できる葬儀社に心当たりがなくても、病院でも紹介してくれますので安心してください。
役所で手続きをする
人が死んだ場合、火葬許可証の発行や死亡届のために役所での手続きが必要です。
葬儀を行う場合、役所での手続きについて葬儀社からの案内や指示がありますが、突然死の場合は葬儀社への連絡が後になることもあります。
葬儀社・菩提寺に連絡をする
突然死が診断されたのち、葬儀社や菩提寺に連絡し、葬儀の準備に移ります。
葬儀社は、葬儀や必要になる各所との連絡も代行してくれます。
菩提寺とは、主に供養のための読経や戒名の用意などについて、打ち合わせを行います。
葬儀社が行う葬儀の段取りの主な内容は下記の通りです。
- 遺体の引き取り、搬送、安置
- 役所など関係各所への手続き代行
- 火葬場の予約調整
- お通夜や葬儀などのスケジュールや内容の打ち合わせや段取り
葬儀社についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をお読みください。
葬儀に関してさらに詳しく知りたい方は、以下から無料で資料を請求できます。
お気軽にお問い合わせください。

みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
遺産相続の手続き
葬儀が終わった後、次のステップは遺産相続の手続きです。
相続対象となる財産には、現金、預金、不動産、投資信託、株式、貴金属やアンティーク、ゴルフ会員権などが含まれます。
遺言書が存在しない場合、遺族間での協議により遺産の分配が行われます。
相続税の申告と納税は、10ヶ月以内に行う必要があり、この期限を逃すと追加の税金が発生するので注意が必要です。
故人の情報が銀行に伝わると、預金口座は一時的に利用停止となります。
しかし、相続人全員の合意が得られれば、この停止を解除し、口座の手続きが可能です。 手続きに際して、以下の書類の準備が求められます。
- 死亡診断書のコピー
- 遺産分割協議書
- 謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 使用していた通帳とカード
遺産相続は複雑なプロセスですが、適切な情報と手続きでスムーズに進めることができます。
スポンサーリンク葬儀日程の決め方
葬儀日程の決め方は、下記でご紹介するいくつかの項目に留意して行うとスムーズです。
日程の決め方
死亡届を済ませ、火葬許可証の発行手続きをしたら、葬儀の日程を決めていきます。
葬儀会場や菩提寺と連絡をとり、会場と僧侶の予定を優先的に抑えておきましょう。
そのあと、親族や関係者へ葬儀の案内を出します。
検視がある場合
突然死では警察による検視によって、遺体を預けなければいけない場合があります。
不審死のときは検視によって遺体がすぐに返されないため、葬儀は執り行えません。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
【ケース別】亡くなった日時と葬儀日程の決め方
人の死は予測できないものです。
突然の死による遺族の心の動揺や、葬儀の日程設定の難しさは計り知れません。
以下では、故人の死亡時刻や状況に応じた葬儀日程の設定方法を詳しく説明します。
一般的な葬儀日程の設定
ケース①:朝から夜までの死亡 故人が朝4時から夜9時の間に亡くなった場合、翌日の夜にお通夜を行うのが一般的です。
具体的な流れは以下の通りです。
- 死亡当日:遺体を自宅に安置
- 死亡翌日:葬儀場への遺体移送、夜にお通夜
- 死亡翌々日:葬儀と火葬
深夜の死亡時の葬儀日程
ケース②:深夜の死亡 深夜11時から夜中2時の間に死亡した場合の日程は以下の通りです。
- 死亡当日:遺体を自宅に移送・安置、夕方に葬儀場でお通夜
- 死亡翌日:葬儀と火葬
事故や突然死の場合の葬儀日程
ケース③:事故や突然死 事故や突然死での死亡は、通常の葬儀よりも日程設定が難しいです。
以下のポイントに注意が必要です。
- 遺体は病院や警察署で検死される
- 検死後、速やかに遺体を引き取る
- 葬儀日程は葬儀社との相談が必要
年末年始の死亡時の葬儀日程
ケース④:年末年始の死亡 年末年始は特に葬儀日程の設定が難しい時期です。
以下のポイントを参考にしてください。
- 多くの火葬場は年末からお正月にかけて休業
- 葬儀社は年中無休で対応可能
- 遺体の保存方法に注意が必要
葬儀日を決める際の重要なポイント
葬儀は故人を偲ぶ大切な儀式です。その日程を決める際には、伝統的な風習や現代の生活スタイルを考慮する必要があります。以下、葬儀日程を選ぶ際のポイントを解説します。
友引の日を避ける理由
友引とは?
友引は、六曜の一つで、良いことも悪いことも引き合う日とされています。
葬儀を行うと他の人の死を引き寄せるという伝統的な考えから、多くの地域で友引の日に葬儀を避ける風習があります。
火葬場の休みに注意
友引の日は火葬場が休みの場合が多いため、事前に確認しておくことが大切です。
僧侶のスケジュールを確認
檀家との関係性
昔からの檀家との関係を大切にする家庭は多いです。
そのため、葬儀日程を決める前に、僧侶の予定を確認することが必要です。
年末年始やお盆の注意点
特に年末年始やお盆は、僧侶が他の法事で忙しいことが多いため、事前の確認が欠かせません。
地域の風習を尊重
火葬の順序
地域によっては、火葬を先に行い、その後に葬儀を行う風習があります。
仮通夜と本通夜
仮通夜と本通夜を分けて行う地域もあります。
地域の風習を知り、適切な日程を選ぶことが大切です。
親族の都合を考慮
遠方の親族の移動時間
特に海外に住む親族は、移動に時間がかかるため、日程の調整が必要です。
事前の連絡が鍵
危篤の際や火葬場の予約前に、親族との連絡を密に取り合うことで、スムーズな日程調整が可能となります。
葬儀は故人を偲ぶ大切な時間です。
伝統と現代のバランスを取りながら、最適な日程を選ぶことで、故人を心から送り出すことができます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
家族が突然死した時の連絡と対応
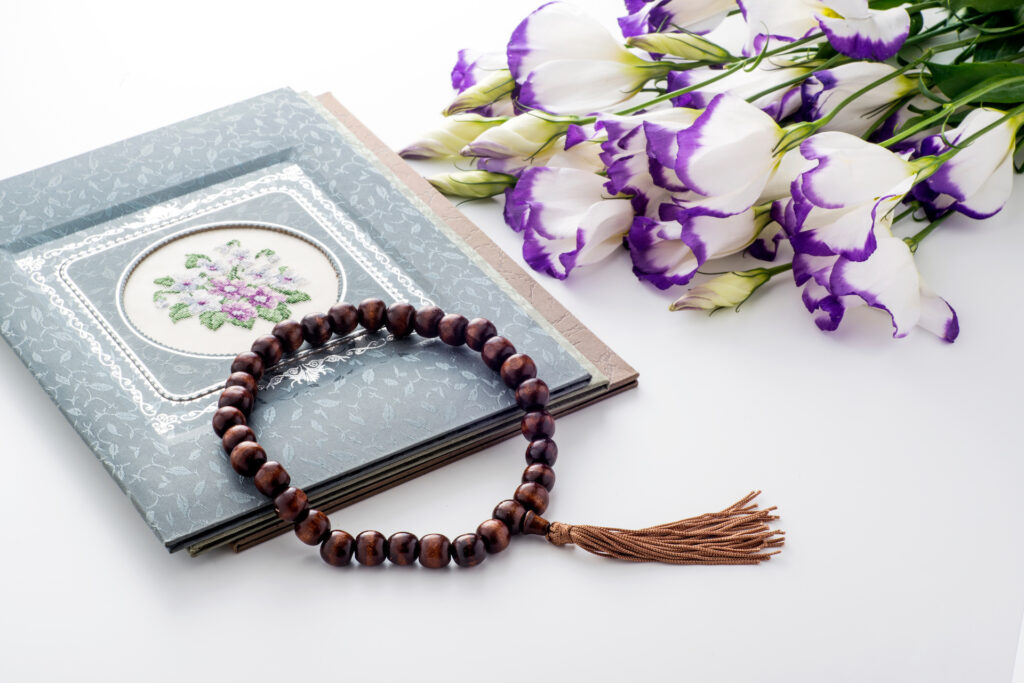
親しい家族や親族が突然なくなってしまった時、呆然としてしまうことだと思います。
しかし、悲しみに暮れている間はありません。
ここでは、親族が急逝してしまった場合の対処法をケースごとにご説明していきます。
病院
事故などが原因で病院へ搬送されていた場合、警察から連絡が入ることになります。
その際には、例え死亡が確認されていても電話で伝えられることはありません。
あくまでも本人確認のために呼ばれるのです。
病院へ行く際は、気が動転していることもあるでしょう。
車の運転は避けてタクシーや公共交通機関を使うことをおすすめします。
万が一に備え、持ち物も準備しておきましょう。
交通費・食事代などのための現金や、本人確認のため、自分の身分証明書とできれば故人の証明証、そして連絡手段のための携帯電話や電話帳などです。
病院への支払いは後日請求となることが多く、現金は10万円ほど用意していれば問題ありません。
病死の場合
病死の場合であれば、病院から直接連絡が入ります。
本人確認を行い、医師から詳しい治療内容と結果の報告がされた後、一緒に死亡確認を行います。
最後に死亡診断書が渡されます。
死因が不明の場合
死因が不明の場合は警察から事情聴取を受けることになるでしょう。
本人確認をし、持病の有無などを伝えます。
後日に死亡診断書のコピーを警察署へ提出するよう求められることもあります。
性犯罪の有無を確認するために死体の検視を行うケースもあります。
自宅などの病院以外
体調の悪化や事故など、自宅や病院以外で親族が倒れていた場合、まずは119番に連絡してください。
状況を報告し、救急車を呼びましょう。
蘇生措置を行っても回復が見込めない場合、警察を呼ばなくてはなりません。
氏名と現場の住所を伝え、待機します。
警察の調査が終わるまでは現状維持を保たなければなりません。
事情聴取と現場検証が終わり、警察から了承が得られれば、ご遺体を布団などに寝かせてあげてください。
事件性があった場合は、検視官による死体の検視が行われます。
死因が分からなければ、検案・行政解剖が行われます。
検案・解剖の終了後にご遺体がもどされます。
葬儀社に連絡し、棺を用意してもらい、一緒に監察医務院へご遺体を引き取りに行きましょう。
お通夜の連絡:適切なタイミングと方法
故人の訃報は、遺族にとっても受け取る側にとっても重いものです。
特に突然の死の場合、遺族は混乱し、どのように連絡すれば良いのか迷うこともあるでしょう。
以下では、お通夜の連絡のタイミングや方法、伝えるべきポイントを具体的に解説します。
連絡のタイミング
ケース①:親戚への連絡
- 三親等以内の近親者:危篤状態や死亡直後に伝える
- それ以外の親戚:お通夜の日時が確定してから伝える
ケース②:友人・職場関係への連絡
- お通夜と葬儀の日時が確定してから伝える
連絡の手段
ケース①:親戚への連絡
- 電話で直接伝える
ケース②:職場関係への連絡
- 電話、電報、メールなどを使用
- 葬儀社に看板を立ててもらう
- 新聞の訃報欄に掲載
ケース③:友人・知人への連絡
- 直接電話で伝える
- 他の友人や知人に連絡を回してもらう
伝えるべき内容
- お通夜の場所と日時
- お手伝いが必要な場合、その旨を伝える
- 家族葬や直葬の場合、その旨を明確に伝える
- 服装や香典に関する指示
お通夜の連絡は、故人を偲ぶ大切な儀式への第一歩です。
適切なタイミングと方法で、故人の遺志を尊重しながら、遺族や参列者の負担を軽減することが大切です。
葬儀に関してさらに詳しく知りたい方は、以下から無料で資料を請求できます。
お気軽にお問い合わせください。

みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
お墓はいつまでに用意すれば良い?

一般的に、亡くなった方は、火葬されたあとに遺骨となって、墓地や霊園などのお墓に埋められます。
ご自身の家が、先祖から引き継がれたお墓をお持ちの方であれば、お盆やお彼岸、年末年始などのタイミングでお墓参りをした経験があることでしょう。
その一方で、現代では、さまざまな事情から、ご自身やご家庭のお墓をお持ちでない方も多くいらっしゃいます。
もし、身内やご自身が突然死してしまった場合、お墓はいつまでに用意しなくてはならないのでしょうか。
お墓選びは一生のうち何回もするものではなく、まとまった費用も必要なため、時間をかけてじっくり取り組む必要があります。
そのため、突然死のあとで慌ててお墓を選ぶのではなく、事前に準備しておく方が無難でしょう。
しかし、万が一身内に突然死があった場合、お墓を事前に用意していない方は少なくないようです。
仮に、お墓を事前に用意できなくても焦る必要はなく、故人の一周忌までにお墓を建てるケースも突然死に限らず多いです。
一周忌までには遺骨を自宅などで保管して、条件の良いお墓を、時間をかけて探すことが推奨されています。
お墓の選び方についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をお読みください。
葬儀に関してさらに詳しく知りたい方は、以下から無料で資料を請求できます。
お気軽にお問い合わせください。
 スポンサーリンク
スポンサーリンク
突然死で亡くなった時のお悔やみの言葉
突然の死に直面した際、適切な言葉を見つけるのは難しいものです。
心の中の悲しみや驚きを言葉にすることは、感情が高ぶる中でなかなか難しいことが多いです。
そこで、突然死で亡くなった方へのお悔やみの言葉の例文をいくつかご紹介いたします。
これらの言葉が、あなたの気持ちを適切に伝える手助けとなれば幸いです。
例文1
このたびはご愁傷様でございます。
突然の事で、悲しみにたえません。
心より、ご冥福をお祈り申し上げます。
例文2
このたびは、誠にご愁傷様でございます。
急なことでお慰めの言葉も御座いません。
こころより、お悔やみ申し上げます
例文3
急な知らせを頂き、本当に信じられない思いでいっぱいです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
死別の悲しみを乗り越えるための5つの方法
死別は人生で最もつらい経験の一つです。
その痛みをどうやって受け入れ、乗り越えるかは、人それぞれ異なります。
以下では、死別の悲しみを乗り越えるための5つの方法をご紹介します。
感情を共有する
故人を悲しむ親戚や友人との対話は、心の癒しとなります。
過去に同じような経験をした人の話を聞くことで、自分も乗り越えられると感じることができます。
また、経験者のブログを読むことも、悲しみを共感し合う手段として有効です。
感情を外に出す
悲しみを内に閉じ込めるのではなく、感情を外に出すことが大切です。
泣きたいときは泣き、感情を自由に表現することで、心の重荷が軽くなることがあります。信頼できる人の前で、自分の感情を正直に表現しましょう。
文字による表現
自分の感情や思いを文字にすることで、心の中の混乱や葛藤を整理することができます。
日記や手紙、ブログなど、形式を問わずに自分の気持ちを書き出すことを試してみてください。
専門家のサポートを受ける
悲しみが強く、日常生活に支障をきたす場合は、カウンセリングを受けることを検討しましょう。
グリーフケアやグリーフサポートを専門とするカウンセラーは、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
自分自身を大切にする
死別の悲しみは深く、心と体に大きな影響を及ぼします。
そんな時は、自分の心と体を大切にし、無理をせずに過ごすことが大切です。
死別の悲しみは一人で乗り越えるものではありません。
周りのサポートや上記のステップを参考に、自分のペースで前に進んでください。
家族の突然死についてよくある質問

一般的な葬儀とは違い、身内の方が突然死をしたケースではなんの心構えもなく葬儀を行うことになります。
ここでは、そんな場合の葬儀についてのよくある質問に具体的にお答えしていきます。
急死した場合葬式は何日後?
通常のお通夜は亡くなった翌日に行い、告別式は翌々日に行うことが一般的ですが、何日後までにやらなくてはならないという決まりはありません。
六曜の友引に当たったり、火葬場の予約が取れないなどさまざまな事情で日付がずれることもあります。
特に急になくなってしまった場合など、親族の予定も間に合わず葬儀の止むに止まれず葬儀の日程を変更することもあります。
急に亡くなった時はどうしたらいい?
自宅や職場など、人が突然無くなった場合には現状維持が鉄則です。遺体には触れず、亡くなったときの状態を保ちましょう。
変死の場合、警察が現場検証と事情聴取を行います。
万が一ご遺体を動かしてしまったら、事件の証拠隠滅を疑われることもあります。
突然死は何歳が多いの?
突然死とは、何らかの病気により発症から24時間以内に死亡してしまった場合の事を言います。
男性の突然死は脳血管障害や心臓病が多く、45歳頃から増え、50代で急増します。
女性は50代から脳血管障害、60代からは心臓病が多くなるようです。
病院で亡くなった時、どんな服を着せたらいいの?
病院で亡くなった場合、一般的には浴衣を着せます。
病院ではエンゼルケアが行われ、遺族や看護師が病院が用意した浴衣に着替えさせるのです。
自宅や葬儀社への搬送後に納棺しますが、その際に死に装束に着替えるというのが自然の流れです。
身内が亡くなったら何日くらい休む?
忌引き休暇は各会社や学校により異なります。
故人との関係性によっても、忌引の日数が違ってきます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
家族が突然死した時のまとめ

ここまで突然死の情報や、葬儀の段取りなどについて解説してきました。
まとめると以下の通りです。
- 突然死とは原因となる病気の発症から24時間以内に死に至ることを指す
- 突然死であっても遺族がすべき葬儀の手順に大きな変わりはない
- もしも突然死を目撃したら、遺体に触れたり動かしたりしない
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
葬儀に関してご不明な点等ございましたら、以下のボタンからお電話をおかけください。
お気軽にお問合せください。

都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2022.11.21
町内会の回覧板で訃報のお知らせをするには?文例や注意点を紹介!
お葬式

更新日:2024.03.30
離婚した父の葬儀で喪主は誰がやる?参列の可否や香典の扱いについても解説
お葬式

更新日:2022.11.18
なぜご遺体の手を組む必要があるの?手を組む理由や注意点も紹介
お葬式

更新日:2022.11.18
会葬御礼は郵送した方が良い?弔問客や代理参列者の対応も説明
お葬式

更新日:2022.11.21
供花を頂いたらお礼はするべき?お礼状の書き方や例文も紹介
お葬式

更新日:2022.11.17
枕飾りのご飯(枕飯)とは?いつまでお供えすればいいの?