お葬式
故人の貯金で葬儀費用を払うには?口座引き出しの方法や相続税控除の対象になる葬儀費用なども解説
更新日:2025.06.17 公開日:2021.07.20

記事のポイントを先取り!
- 葬儀費用は故人の貯金から支払える
- 銀行が訃報を確認すると口座が凍結される
- 凍結された口座から現金を引き出す方法は2つ
葬儀は多くの方にとって急に訪れるもので、葬儀費用も遺族の方にとって小さくない負担です。
そのため、喪主や遺族の方の中には故人の貯金を葬儀費用に充てたいという方もいらっしゃると思います。
そこで、この記事では故人の貯金を葬儀費用に充てられるかについて解説します。
故人の凍結された銀行口座からお金を引き出す方法、相続控除などについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 故人の貯金から葬儀費用を支払える?
- 故人の貯金で葬儀費用を支払う際の注意点
- 故人の銀行口座が凍結する理由
- 口座凍結後に貯金を引き出す方法
- 故人の口座から葬儀費用を引き出す際の注意点
- 葬儀費用の全額が相続税控除の対象にはならない
- 葬儀費用以外に使うと相続放棄ができない
- 生前にできる葬儀費用の準備
- 葬儀費用がないときの対処法
- 葬儀に必要な費用・内訳
- 故人に身寄りがない場合の葬儀費用
- 故人の預金や葬儀費用に関するよくある質問
- 葬儀費用を故人の貯金で払うことのまとめ
故人の貯金から葬儀費用を支払える?
葬儀費用は、故人の貯金から支払うことができます。
葬儀費用を故人の貯金から支払う場合には、相続税の控除対象となるのは「遺体の搬送費用」や「僧侶へのお布施・戒名料・お通夜・告別式・火葬や埋葬・納骨にかかる費用」などです。
「香典返し」や「葬儀後の法要費用」などは葬儀に直接関係ないと見なされます。
しかし葬儀に直接関係のないことに故人の貯金を使用すると、相続放棄ができなくなったり、相続税控除の対象にならない恐れがあります。
葬儀の費用は平均195万円程かかると言われているので、故人の貯金を充てられるのは大きなメリットと言えます。
しかし、その条件や内容についてきちんと理解して処理を行わなければ、後々トラブルになりかねません。
葬儀の費用について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
故人の貯金で葬儀費用を支払う際の注意点

急な訃報で葬儀を執り行うこととなり、葬儀費用の捻出に困る方もいることでしょう。
そういう場合には、故人の貯金から葬儀費用を支払うことができます。
この章では、葬儀費用を故人の貯金で支払う際、相続放棄の必要性が出た場合に注意すべきことを4つの項目に分けて解説します。
高額の葬儀
相続放棄をすれば故人の貯金から、葬儀費用を支払うことができないと思われがちです。
身分相応で一派的に営まれる最低限の葬儀費用に充てることは、法律で認められています。
しかし、豪華で高額の葬儀を執り行うと、相続放棄が認められなくなる危険性があります。
債権者の債権を減らしてまで、高額の葬儀を執り行うのは非常識と見なされるためです。
高額で規模の大きい葬儀を執り行わずに、必要最小限の葬儀を執り行うようにしましょう。
念のために、葬儀代の詳細を記した領収書や明細書は保管しておくと、裁判所から提出を求められたときに安心です。
財産的価値のあるものの処分
遺品は、相続を放棄した人でも他の相続人が引き取るなどしない限り、自分の財産と同様に保管管理する義務が生じます。
遺品のなかでもブランド品や、貴金属類・車など財産的価値のあるものは注意が必要です。
遺品を隠匿したり、処分してしまうと「法定単純承認」になり相続放棄は無効になります。
ただし社会通念に照らし、故人の遺品を形見分けとして持つ程度なら問題ありません。
後のトラブルを避けるため、処分に困った時は弁護士などへの相談をおすすめします。
葬儀と関係ないものに使わない
葬儀と関係ないものに故人の貯金を充てるのは、相続放棄の対象外となるためNGです。
香典返しや初七日・四十九日法要・宿泊費・喪服代などの費用が、これに該当します。
仏壇や墓地・墓石の購入費用は高額になるため、特に注意が必要です。
凍結前に引き出さない
口座が凍結すると引き出せないため、凍結前に葬儀費用を引き出す人もいるかと思います。
相続放棄の手続きを済ませていても被相続人が危篤状態の時に、お金が動いた事実が判明してしまった場合、相続放棄が認められなくなります。
口座凍結前は、故人の貯金から絶対に引き出さないように注意しましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
故人の銀行口座が凍結する理由
銀行などの金融機関は、人が亡くなると口座を凍結させます。
口座が凍結されると、預金の引き出し・預け入れ・振り込み・引き落としなど、一切の手続きができなくなります。
口座を凍結する理由は、不正利用や遺産相続争いを防ぐためです。
銀行に預けてあるお金は、故人の「遺産」にあたります。
預けてあるお金はキャッシュカードがあり、暗証番号さえ分かれば引き出すことは容易です。
そのため、親族が勝手にお金の引き出しを行い、遺産相続のトラブルに発展することは珍しくありません。
銀行としてはそのトラブルに巻き込まれたくはないため、口座の凍結という形を取ることにしています。

口座凍結後に貯金を引き出す方法

口座凍結後に葬儀費用のためにお金を引き出す方法は2つあります。
仮払い手続きと相続手続きです。
葬儀の準備に追われ手続きが多く、対応が難しい場合もあると思います。
口座凍結後にお金を引き出す手続きと、忙しいときの対処方法を解説します。
仮払い手続き
仮払い手続きは、遺産相続の話し合いが終わる前に相続人が預金を引き出せる制度です。
引き出す金額は、基本的に預金残高の3分の1を相続人数の合計で割った金額となります。
しかし、1口座150万円を超えて引き出すことはできません。
必要書類は以下のものとなります。
- 被相続人(故人)の除籍謄本、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
- 故人の死亡診断書(写し可)
- 相続人の戸籍謄本と本人確認書類
- キャッシュカードや預金通帳、届出印
- 葬儀費用の見積書や請求書など
戸籍謄本は、現住所ではなく本籍地で取得となります。
手続きに時間がかかってしまわぬよう、必要事項を把握しておくことが大切です。
相続手続き
口座凍結後にお金を引き出す方法に相続手続きを行うという方法があります。
預金だけ先に遺産分割協議を行うことも可能です。
相続手続きさえ完了してしまえば銀行口座の凍結を解除することができます。
相続手続きに必要書類は以下のものとなります。
- 被相続人(故人)の除籍謄本か戸籍謄本か改製原製原戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
- 法定相続人全員の印鑑証明書(発行より3ヵ月以内のもの)
- キャッシュカード、預金通帳、銀行印
- 葬儀費用の見積書
相続や故人の資産について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
亡くなった人の口座凍結や遺族年金の相続|故人の資産の取扱いについて
裁判所に仮処分を認めてもらう
仮払い制度では口座から引き出せる金額に上限がありますが、上限金額よりもお金が必要になる場合もあるでしょう。
そうした際は裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申請する必要があります。
申請が通れば、預貯金の全てまたは一部を引き出すことが出来ます。
ただし仮処分の申請にはさまざまな条件があるので、事前に確認しておきましょう。
仮処分の申請に必要な条件
- 遺産分割の調停・審判の申し立て
- 他の相続人らの利益を害さないこと
- 債務の弁済や生活費の支弁
- 預貯金の払い戻しの認められる事情
専門家に依頼することも可能
口座凍結後にお金を引き出す手続きは、必要な書類も多く時間がかかります。
葬儀の準備と並行して手続きを進めるのは容易ではありません。
そのようなときは、弁護士や行政書士といった専門家に依頼をしましょう。
必要書類の収集や、手続きを代わりに行ってもらうことが可能です。
手続きを代行してもらう場合は委任状の記載などが必要になります。
しかし、弁護士や行政書士の指示に従って書類を作成すれば問題ありません。
費用は依頼する場所ごとに異なるため、事前によく確認する必要があります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
故人の口座から葬儀費用を引き出す際の注意点
故人の貯金を口座から引き出す際には、いくつか注意点があります。
ここではその注意点について詳しくご説明していきます。
相続人間同士の話し合いをすること
故人の貯金を引き出す際には、相続人間での事前の話し合いが必要です。
名義人が亡くなった後、口座が凍結される前に相続人が預金を引き出すケースも少なくありません。
しかし、これは他の相続人から「貯金を不正に引き出した」と思われ、トラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
最低限の金額に留めておく
自身の相続分を超えて貯金を引き出さないことも重要です。
自身の相続分よりも多く引き出した場合は、他の相続人との間でトラブルが発生する可能性があります。
故人の口座から貯金を引き出す場合は、必要最低限の金額に留めておくことをおすすめします。
領収書・明細書を保管しておく
葬儀費用を故人の貯金から支払う際は「いつ」「どこで」「何に」使用したかを分かるようにしておく必要があります。
そのため、故人の貯金を引き出した場合は領収書や明細書を保管しておくことが重要です。
これらの書類があれば、故人の遺産を勝手に使っていないことを他の相続人に対して証明できます。
また、相続税控除の金額の明細にもなり、「財産の使用」にはあたらないという証拠としても使用可能です。
僧侶へのお布施など、領収書の用意が難しいケースでは、自身で作成したメモを代用することが可能です。
手続きに不備があると、大きな損失が発生する可能性があります。
貯金の使用は葬儀の範囲内に収めておきましょう。
慣れない手続きで忙しくても、必要なものはきちんと残すよう注意してください。
葬儀費用の全額が相続税控除の対象にはならない
葬儀費用には相続税控除の対象になるもの、ならないものがあります。
控除の対象になるか否かの判断は、葬儀を実施する際に一般的に掛かる費用か、葬儀とは直接関係ない費用かどうかによります。
葬儀費用の控除対象
葬儀費用の控除対象となるものは以下のとおりです。
- 遺体の搬送費用
- 僧侶へのお布施・戒名料などのお礼
- お通夜・告別式に掛かる費用
- 火葬料・埋葬料・納骨費用など
- 死亡診断書の発行費用
- 葬儀で必要となる飲食費
これらの費用は、葬儀で一般的に必要なものとみなされ、相続税から控除できます。
葬儀費用の非控除対象
相続税控除の対象にならないものは以下のとおりです。
- 香典返し
- 初七日・四十九日など、葬儀後の法要費用
- 墓石・墓地に掛かる費用
- 仏壇・仏具などの購入費用
- 遺体の解剖費用
- 遠方の親族の宿泊費
- 喪服代
これらの費用は葬儀と直接関係があるとは言い難く、相続税の控除対象とはなりません。
葬儀とは直接関係ないとされる費用に、故人の貯金を使用してしまうと、新たな問題が発生するケースもあります。
どのような問題が発生するのか、次の項目で詳しく解説します。
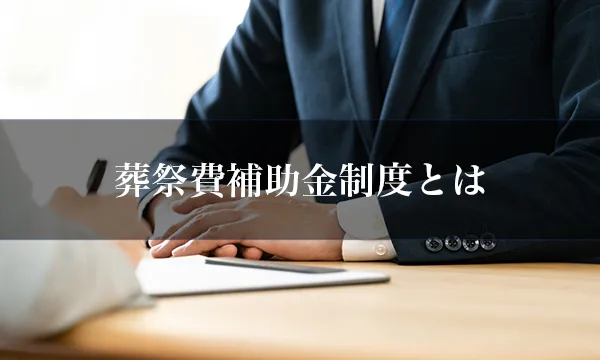
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀費用以外に使うと相続放棄ができない
相続放棄とは
相続でも負債があれば負債も相続する必要があります。
「相続」とは故人の財産を引き継ぐことで、相続放棄は大半の場合、故人に負債があった場合に行われます。
相続放棄をできない場合、思いがけない負債を抱えてしまうことになりかねません。
遺産の相続のルールを正しく理解し、故人の貯金の取り扱いには十分注意してください。
相続放棄ができない場合
葬儀費用に関しては故人の貯金から費用を出しても相続放棄ができます。
しかし、故人の貯金を、葬儀とは直接関係ない項目に使用すると「相続を受け入れた」と判断され、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
あまりにも高額な葬儀を行った場合や財産的価値のあるものを処分した場合にも相続放棄をすることができないことがありますのでご注意下さい。
死亡保険金や故人の身の回りの品、医療費の支払いなどは相続放棄に影響はないので使用しても問題ないです。

生前にできる葬儀費用の準備

葬儀費用を故人の貯金から支払う手続きは、必要書類も多く、所要時間もかかります。
特に、口座が凍結された場合や相続の手続きが必要な場合、1週間から1ヶ月以上の時間が必要となることがあります。
葬儀費用は葬儀が行われてから約1週間後までに支払う必要があるため、手続きが間に合わない可能性もあります。
また、故人の貯金を引き出すためには、さまざまな条件や手続きが必要で、これらを満たさないと引き出すことができません。
いざというとき困らないために、生前に対策をしておくこともおすすめです。
ここでは、事前にできる対策を紹介します。
- 生命保険などに加入しておく
- 互助会や葬儀信託を利用する
- 葬儀代を生前に引き出し自宅に保管しておく
- 故人の許可を得てから引き出す
- 生前に引き出した現金も申告する
それぞれどのような対策か、詳しく解説します。
生命保険などに加入しておく
葬儀費用に故人の貯金を使用しない1つ目の対策は、生命保険に加入しておくことです。
葬儀を執り行う人を受取人にしておけば、葬儀費用に充てることができます。
死亡保険金は、死亡届のコピーを保険会社に送ることで、約1週間以内に支払われます。
また、生命保険の他にも葬儀保険という保険もあります。
葬儀保険は、少額短期保険(ミニ保険)の1種です。
生命保険よりも葬儀に特化した内容となっています。
葬儀保険の死亡保険金は300万円以下ですが、葬儀の準備には十分な金額といえます。
葬儀保険は一般的な健康保険よりも加入要件が緩く、保険料も割安という特徴があります。
加入する際医師の診査が不要のため、高齢の方や持病のある方には葬儀保険がおすすめです。
互助会や葬儀信託で事前に費用を準備
2つ目の対策は、互助会や葬儀信託で事前に費用を準備することです。
互助会では、毎月一定の金額を積立てることで葬儀費用に充てることができます。
積み立てたお金を自由に使えなかったり、プランが限定されていたりするので注意も必要です。
一方、葬儀信託は互助会と比べ新しいサービスで、葬儀費用を銀行に信託するものです。
葬儀社が倒産してしまうなどの心配がないのが特徴です。
また、生前に自分の希望する葬儀プランを作成することもできます。
葬儀代を生前に引き出し自宅に保管しておく
3つ目の対策は、葬儀に必要なお金をあらかじめ引き出し、自宅に保管しておくことです。
銀行口座の凍結による心配もなく、遺族がお金を引き出す必要もなくなります。
まとまったお金を高齢者が手元に置いておくのはトラブルになる恐れがあり大変危険です。
葬儀に必要なお金を自宅に保管する場合は、家族とよく相談し、トラブルが起きないよう配慮する必要があります。
生前に貯金を引き出した場合の注意点
【故人の承諾を得てから引き出す】
故人の承諾もなく故人名義の口座から葬儀費用のためとはいえ無断で預貯金の引き出しをすると、遺産相続の話し合いの時に他の相続人とトラブルになる可能性があります。
無断で故人の遺産を流用し、故人の財産を損失させたことになるためです。
そのため、他の相続人から不当利得返還請求を受けることになる可能性があります。
故人の生前に預金を引き出す場合は、必ず故人の許可を得るようにしてください。
認知症などで許可を得ることが難しい場合は、法定後見制度を申し立てると代理で口座の手続きを行えます。
【生前に引き出した現金も申告する】
生前に故人の口座から引き出し、自宅で保管している現金を手許現金と呼ばれます。
故人が所有していたすべての財産は相続財産として計上されます。
これには手許現金も含まれます。
しかし葬儀費用は相続税から控除できるので、葬儀費用のための手許現金は計上しなくていいと考える方もいますがそれは間違いです。
相続税の算出は、故人の死後の預金と手許現金の合計から葬儀費用を引いたものになります。
したがって、葬儀費用は控除されるからと手許現金を計上しないと、
○死後の預金500万+生前に引き出した現金200万-葬儀費用控除200万=財産300万
×死後の預金500万-生前に引き出した現金200万-葬儀費用控除200万=財産100万
このように葬儀費用が二重に控除されることになってしまいます。
二重控除は税務調査の際に問題になるので、生前に葬儀費用として引き出した場合は必ずその金額も申告するようにしてください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀費用がないときの対処法
葬儀や葬式費用がないときの対処法は、以下の通りです。
- 葬儀費用を抑えた葬儀形式にする
- 葬祭扶助を利用する
- 埋葬費・葬祭費を請求する
- クレジットカード払いにする
- 葬儀ローンを利用する
- 葬儀費用が抑えられる葬儀形態を選ぶ
- 故人の遺産や生命保険を利用する
費用を抑えた葬儀形式にする
一般葬の費用相場は約200万円程度です。
通夜や告別式を行わずに火葬だけを行う直葬や、通夜を行わず告別式と火葬だけを行う一日葬は一般葬より安い金額で葬儀を行うことができます。
参列者も親族や親しい友人だけで行うので、飲食接待などの負担がかからないのもメリットです。
葬祭扶助制度を利用する
葬祭扶助とは、遺族が経済的な事情で葬儀を行えない場合に自治体が葬儀を行うための最低限の費用を負担してくれる制度です。
生活保護葬や福祉葬、民生葬などとも呼ばれます。
しかし、受け取る条件として生活保護を受けていることなど、条件がかなり限られていますので注意が必要です。
支給される金額は自治体によって違いますが、大人の葬儀で20万円が平均となっています。
葬祭扶助で負担してもらえる金額は火葬のみとなっており、祭壇や告別式などの費用は負担してもらえません。
埋葬料・葬祭費を請求する
健康保険や自治体から給付される埋葬料・葬祭費を自治体に請求すれば、葬儀費用に利用できます。
埋葬料とは、生前故人が加入していた健康保険から、埋葬の費用を一部負担されるお金です。
故人が会社員の被扶養者であっても支給され、給付金額は一律で5万円です。
被保険者の死亡を受けて給付されるので、忘れないようにしましょう。
葬祭費とは、故人が自営業で国民健康保険に加入してた場合や、後期高齢者医療制度の被保険者であった場合に支給されます。
この場合の給付金は、自治体によって異なりますが、大体1万円〜7万円程度です。
葬祭費は、埋葬料とは違い実際に行った葬儀に対し給付されます。
クレジットカード払いにする
カードが利用できる葬儀社であれば、分割払いで支払うことも可能です。
ただし分割で支払う場合、一般的なローンより金利が高くなってしまう場合もありますので、その点は注意しましょう。
葬儀社によっては、全てカードで支払うことができるところもあれば、一部は現金で支払わなければならない項目もあります。
分割で支払えないなどルールは様々なので、事前にしっかりと確認しましょう。
葬儀ローンを利用する
葬儀社が行っている葬儀ローンを利用する方法もあります。
葬儀社によっては、金融機関と提携して専用のローンを組んでくれる場合もあります。
ただし必ず返さなければならないお金なので、返す当ても無いくらい生活に困っている場合には、あまり利用しない方が賢明です。
金利も高くなる可能性もありますので、その点にも注意しましょう。
葬儀費用が抑えられる葬儀形態を選ぶ
【市民葬・区民葬】
市民葬・区民葬とは、各自治体が市民・区民向けのサービスとして行っている葬儀プランです。
葬儀会社と協定して料金を安く設定し、葬儀を行えます。
市民・区民向けのサービスということで、簡素ながら安価で葬儀を行うことができるというありがたい制度です。
葬儀費用には祭壇、霊柩車、火葬料金が含まれています。
ただ、まだ制度そのものが無い自治体も多く、日本全体ではまだまだ定着しているとはいえません。
なので、事前に自分の住む街に制度があるかどうかを、しっかり確認するようにしましょう。
【家族葬】
家族葬は家族や親族、親しい友人などごく限られた人だけで行われる小規模な葬儀のことです。
家族葬では、参列者数は10人~30人程度で行われることが多く、通夜や告別式、火葬がという流れで行われるのは一般葬と同じです。
家族葬の全国平均費用はおおむね110万円です。
しかし、葬儀者からの香典を辞退することが多いため、費用は自己負担となります。
家族葬のメリットは親しい身内だけでゆっくり故人を見送ることができる点です。
一般葬では、参列者へのあいさつや受付、接客などの対応が必要ですが、家族葬ではそういった手間を省くことができます。
その他、参列者の人数も事前に把握しやすい点もメリットの1つです。
デメリットとしては、故人の葬儀に参列したい人がいた場合でも、喪主からの招待がなければ葬儀に参列できない点などがあります。
【火葬式】
通夜や告別式を省略して、火葬のみで済ませる葬儀のことを火葬式といいます。
葬儀にかける費用をおさえたい場合や、故人が質素な葬儀を希望した場合に火葬式が選ばれることが多いようです。
通夜や告別式の費用がかからないため、費用相場はおおむね20万円ですみます。
準備や式にかかる時間も短く、葬儀社スタッフとの打ち合わせも不要です。
そのため、参列者がご高齢の場合でも身体的負担を軽減できます。
ただし、菩提寺の了解を得ないで火葬式をおこなった場合、親戚からクレームが来たり、菩提寺から納骨を拒否されたりするトラブルが生じる可能性もあります。
火葬式を行う場合は親戚や菩提寺の理解を得ておくことが大切です。

故人の遺産や生命保険を利用する
故人の遺産や生命保険を葬儀費用に充てる方法もあります。
ただし、相続税が絡んだり、遺産相続人の同意が必要など、家庭の事情によっては困難な場合もありますが、家族間で納得ができていれば十分に有効な利用方法です。
もし遺産で賄うのが難しいなら、保険会社の生命保険を利用する手もあります。
生命保険の保険金は、死亡保険金を受け取る人の財産となっているので、請求すればすぐにお金を引き出せるので、いざと言う時に備えておくのも手です。
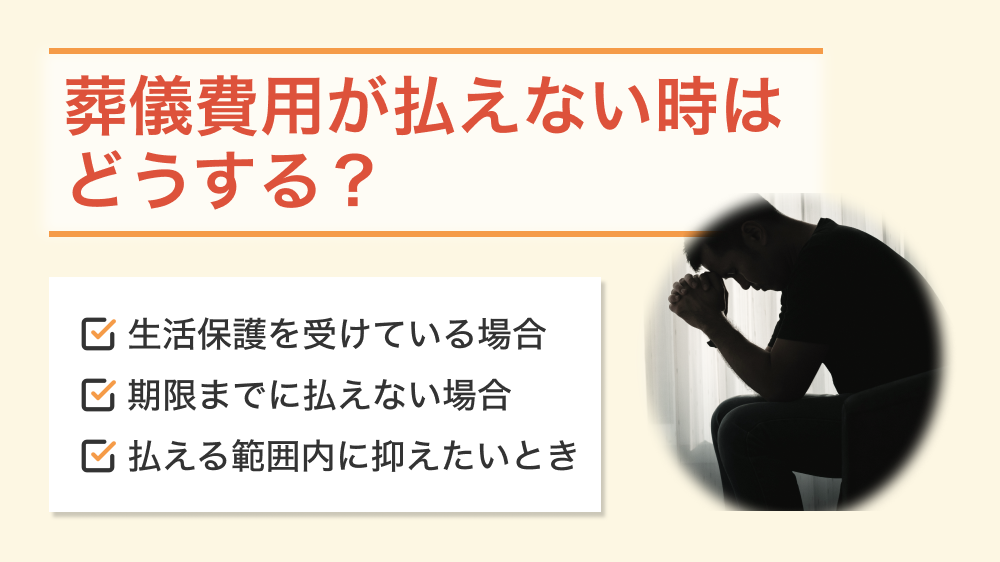
上のグラフは、みんなが選んだ終活が葬儀を行った人を対象に独自に調査した結果です。
家族葬は47.6%と大半を占めており、現在浸透し始めている葬儀形態であることがわかります。
家族葬では、参列者数は10人~30人程度で行われることが多く、通夜や告別式、火葬がという流れで行われるのは一般葬と同じです。
家族葬の全国平均費用はおおむね110万円です。
しかし、葬儀者からの香典を辞退することが多いため、費用は自己負担となります。
家族葬のメリットは親しい身内だけでゆっくり故人を見送ることができる点です。
一般葬では、参列者へのあいさつや受付、接客などの対応が必要ですが、家族葬ではそういった手間を省くことができます。
その他、参列者の人数も事前に把握しやすい点もメリットの1つです。
デメリットとしては、故人の葬儀に参列したい人がいた場合でも、喪主からの招待がなければ葬儀に参列できない点などがあります。
葬儀に必要な費用・内訳

【葬儀の種類ごとの費用相】
| 葬儀の種類 | 費用相場 |
| 直葬(火葬式) | 20〜50万円 |
| 一日葬 | 40〜100万円 |
| 家族葬 | 50〜150万円 |
| 一般葬 | 約195万円 |
葬儀費用の相場は、葬儀の種類によっても違ってきます。
葬儀の種類には、火葬のみを行う直葬、葬儀と告別式を1日で行う一日葬、親族なごく親しかった友人だけで行う家族葬、広く参列者を集う一般葬などがあります。
葬儀形態ごとの費用相場は以下の通りです。
- 直葬(火葬式):20〜50万円程度
- 一日葬:40〜100万円程度
- 家族葬:50〜150万円程度
- 一般葬:195万円程度
自分の葬式代としてもこれだけの費用を用意する必要があります。
葬儀の種類別の費用について、以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
葬儀の種類別費用|家族葬・一日葬・直葬(火葬式)一般葬の違いや相場、内訳

【葬儀費用の内訳(平均相場)】
| 項目 | 平均費用 |
| 葬儀にかかる費用 | 119万1,900円 |
| 接待費用(通夜振る舞い等) | 31万3,800円 |
| 返礼品・礼状 | 33万7,600円 |
| 宗教者へのお礼(お布施等) | 23万6,900円 |
葬儀費用の内訳は、葬儀にかかる費用、接待費用、宗教者へのお礼になっています。
それぞれの詳細については以下のとおりです。
葬儀にかかる費用
葬儀にかかる平均費用は119万1,900円です。
葬儀にかかる費用の内訳は以下のものになります。
会場費・生花・祭壇・棺・衣装・遺影・枕飾り・司会・スタッフの人件費・寝台車・霊柩車・安置料・湯灌・骨壺・骨箱・ドライアイス・火葬場手続の代行・火葬料・受付
接待費用
参列者の通夜振る舞いなどの飲食にかかる費用の平均額は31万3,800円です。
返礼品や礼状などの費用の平均額は33万7,600円です
宗教者へのお礼
通夜・葬式・火葬場での読経のお布施やの平均金額は23万6,900円です。
僧侶の交通費の御車代や、食事に招かない場合は御斎料を渡す場合があります。
葬儀費用準備の注意点
自分の葬儀費用を準備するときの注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。
葬儀そのものにかかる費用に関しては、葬儀社ごとに葬儀の種類に応じた基本プランがあります。
基本プランの内容をさらにグレードアップする場合、追加料金が必要になります。
接待にかかる費用は、標準的な人数分の費用が含まれていることが多いです。
参列者がさらに増えるとその分の追加費用が必要です。
仏教の場合、お布施という名目で読経や戒名代などを渡します。
お布施は、宗教・宗派、寺院や僧侶等の格の違い、戒名の格の違いなどによっても大きく違ってくるでしょう。
仏教の場合で、葬儀社を経由して僧侶に依頼するケースでは比較的料金体系がはっきりしています。
しかし、直接菩提寺に依頼する場合や、仏教以外の宗教の場合などは、費用がわかりにくいので、菩提寺や教会などに確認するようにしましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
故人に身寄りがない場合の葬儀費用
故人に身寄りがなく、相続人や扶養義務者が見つからない場合、故人の葬儀費用は残された貯金などの遺留金から支払われます。
以下で、故人に身寄りがない場合の火葬や費用の支払いがどのように行われるかご紹介します。
故人が残した貯金などの遺留金から支払う
故人に身寄りがない、または身元が不明で火葬などの葬祭を行う人が見つからない場合は、故人が亡くなった場所の市区町村が代わりに火葬を行います。
その際の葬儀費用は、故人が残した貯金や有価証券などの遺留金から充てます。
しかし、必ずしも葬儀費用を遺留金で賄えるとは限りません。
遺留金では葬儀費用が足りない場合、故人の火葬を代わりに行う市区町村が葬儀費用の立て替えを一時的に行い、都道府県に葬儀費用の不足分の負担を求める手続きが行われます。
葬儀費用を支払っても遺留金が余った場合
故人の貯金などの遺留金で葬儀費用を賄えない場合は、市区町村が一時的に立て替えますが、一方で遺留金が余る場合もあります。
身寄りがなく、相続する方が見つからない場合は、相続財産管理制度を活用して相続財産の管理人を選任するか、弁済供託制度を活用して財産整理を行います。
弁済供託制度は、遺留金の管理を国家機関の供託所に任せる制度です。
故人の預金や葬儀費用に関するよくある質問

故人の預金は引き出せますか?
口座名義人の死亡を銀行が確認すると、その口座はすぐに凍結されます。
口座が凍結されると、相続人でも故人の遺産を引き出すことはできません。
口座預金は、名義人が亡くなると相続財産となるので、銀行は相続人が決まるまで遺産争いなどのトラブルを避けるために口座を凍結させます。
死亡後の葬儀費用はいくらですか?
葬儀にかかる費用の相場は、全国平均で約127万円です。
故人の貯金を葬儀費用に充てることができます。
しかし、故人の銀行口座が凍結されると手続きが必要になるなどの条件があるので、注意しましょう。
親の葬儀費用は誰が負担しますか?
基本的には喪主が費用を負担します。
喪主は一般的に故人の配偶者や子供、兄弟姉妹がなります。
喪主になることや、費用の負担に関する明確な決まりはありません。
最終的に誰が支払うのかを家族間ではっきりとするようにしましょう。
預貯金の仮払い制度とは?
2019年の相続法の改正により「預貯金の仮払い制度」が新設され、個人名義の預貯金口座からの、葬式代など当座の必要な資金の仮払いが可能になりました。
故人に故人名義の預貯金口座があったとしても、故人の死亡の時点で故人の遺産となり、口座は凍結されます。
そのため、これまでは、遺産分割の協議・手続きが終了するまでは、故人の口座にあるお金は葬式代などに使用できませんでした。
人が亡くなった場合は葬儀費用が必要です。
葬式代は一般的には、通夜・告別式・火葬にいたるまで100万〜200万円程度の費用が必要です。
さらに、お墓を建てるために150万〜300万円程度の費用がかります。
そのうえ、これまで故人の収入によって世帯の家計がまかなわれていた場合は、遺族の生活費もカバーしなければなりません。
そういった問題を解決するために、2019年の預貯金の仮払い制度が新設されたのです。
たとえ遺産分割前であっても、単独相続人が、葬儀などに必要な費用なら故人の預貯金から引き出すことができるようになりました。
葬儀費用で相続税控除になるものならないものとは?
葬儀費用の一部は相続税控除の対象となります。
これには、ご遺体の搬送費用、死亡診断書の発行費用、火葬費用、葬儀社への費用、僧侶へのお布施や戒名料、読経料、お通夜や葬儀での飲食費、手伝い係への心付け、埋葬・納骨費用、葬儀場までの交通費などが含まれます。
しかし、初七日・四十九日などの法要費用、香典返し、墓地・墓石の購入費用、解剖費用、喪服代、遠方親族の宿泊費用、仏壇・仏具の購入費用などは控除対象外です。
親の葬儀代は誰が払う?
親の葬儀費用の負担は喪主によるのが基本とされています。
とはいえ、親の葬儀の喪主を誰にするのかや、費用を誰が負担するのかは明確な決まりがあるわけではありません。
葬儀が行われる時、誰が費用を負担するのかは大きな問題です。
親の葬儀が行われる場合、長男・長女が喪主になることが一般的のようです。
しかし、親の葬儀費用については、兄弟で話し合って分担するケースがよく見られます。
特に、喪主が葬儀費用を支払うだけの財力を持たない場合は、兄弟や親族の援助に頼らざるを得ないでしょう。
実家の親の香典はいくらが相場?
一般に香典を出す場合の相場は1~3万円が相場です。
実家の親が亡くなった場合の相場はまた違ってくるのでしょうか。
実家の親の場合の相場はどれくらいなのか迷う人も多いのではないかと思います。
葬儀に参列する場合の香典の相場は3,000円~1万円程度のことが多いのですが、参列できない場合の香典の相場はもう少し高額です。
親族が亡くなった場合、基本的に3万円~5万円が相場といわれています。
実家の親が亡くなった場合の香典も、親族の相場にしたがって3万円~5万円にするのが妥当です。
いずれにしても、香典を出す場合の金額については、その人の地位や年齢、地域の特性もあるので事前にチェックしておくようにしましょう。

みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀費用を故人の貯金で払うことのまとめ

ここまで、葬儀費用を故人の貯金で支払う方法について解説してきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 故人の貯金で葬儀費用の支払いに使うことができる
- 葬儀費用を凍結した口座から支払う方法は、仮払い手続きと相続手続きがある
- 葬儀費用を故人の貯金から支払う場合は、支払いの明細を分かるようにしておく
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

袴田 勝則(はかまだ かつのり)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴25年以上。当初、大学新卒での業界就職が珍しい中、葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから皇族関係、歴代首相などの要人、数千人規模の社葬までを経験。さらに、大手霊園墓地の管理事務所にも従事し、お墓に納骨を行うご遺族を現場でサポートするなど、ご遺族に寄り添う心とお墓に関する知識をあわせ持つ。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2025.06.17
互助会の解約には何が必要?退会方法やかかる手数料、返金はいくらかなどを解説
お葬式

更新日:2024.01.10
合同葬とは?社葬や一般葬との違いや相場、マナーについて解説
お葬式

更新日:2023.10.20
湯灌(湯かん)は何をするの?湯灌の目的や費用相場なども紹介
お葬式
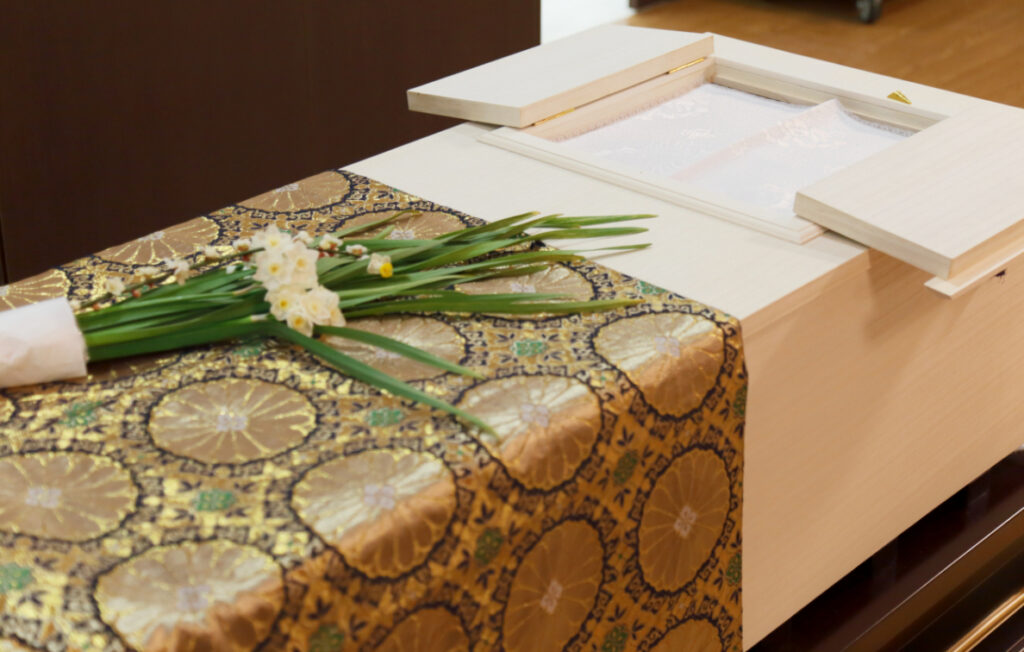
更新日:2024.02.03
遺体搬送車とは?遺体搬送車の車種や霊柩車との違い、搬送料金についても解説
お葬式

更新日:2023.11.12
霊柩車の利用料金は?霊柩車の値段や霊柩車の種類、車種についても解説


