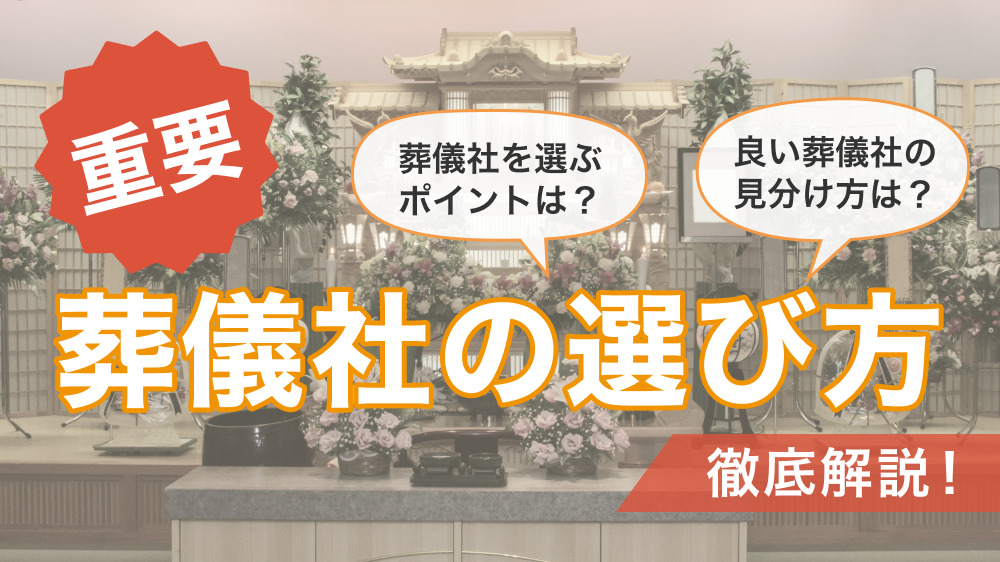終活
家族が余命宣告されたら?家族や本人の対応について紹介
更新日:2024.02.04 公開日:2022.08.09

記事のポイントを先取り!
- 家族は治療方針の検討等をする
- 本人は終活をはじめたりする
- 本人へ余命は伝えるべきである
- 余命は慎重に伝える
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
【みんなが選んだお葬式】
もしも家族が余命宣告されたら虚脱状態になり、どうすればいいのかわからなくなることもあるでしょう。
このような時に家族や本人はどのような対応をとればいいのでしょうか。
この記事では、家族が余命宣告された際の家族や本人のとるべき対応について詳しく解説します。
本人に余命を伝えるべきかについても触れているので、ぜひ最後までお読みください。
みんなが選んだ終活では365日24時間葬儀に関するお悩みに対応しています。
葬儀にかかる料金などにも回答しますのでぜひお申し付けください。

都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
余命宣告とは
余命宣言とはどのようなものなのでしょうか。
余命宣告する目的
余命宣告とは、病気などの対処ができずに医者から余命を告げられることです。
とはいえ、余命宣告で言う余命とは、この病気の場合は◯カ月後に亡くなる人が多いとう予想値にすぎません。
どうして余命宣告をするのでしょうか。
その目的は患者に覚悟をしてもらうためです。
つまり残された人生を大切に生きることの重要性を訴えているのです。
たとえば、父親のがんが悪化して、主治医から「余命はあと3カ月です」と言われたとしましょう。
余命宣告を聞いた家族は、お父さんの余命はあと3カ月しかないのかと愕然となることでしょう。
しかし、気持ちを切り替えて今を大切に生きることの大切さを考えましょう。
いまを大切に生きなければ、長生きしてもしょうがないと思うようになるかもしれません。
今を必死になって生きることで、人生の質を高めることができるのです。
そして、3カ月後にたとえ父親が亡くなったとしても、悲しさのなかにも父とともに充実した時間を過ごせたと自分に言い聞かすことができるでしょう。
余命宣告は外れることもある?
余命宣告は、データや資料をもとに算出したものであり、外れることもあれば早まることもあります。
余命宣告を受けると、生きる可能性がなくなってしまったととらえる人もいるでしょう。
余命宣告の余命は統一的なルールはなく、医師によっても違ってきます。
がんを患った際の余命宣告の指標となるのは、臨床実験での統計データであり、正確な自分や家族の寿命というものではありません。
余命宣告を受けると、必ず死がすぐにやってくるので、もはや生きていてもしょうがないと思うかもしれません。
しかし、余命宣告を受けてもその後回復するケースも見られます。
また、余命宣告の期間と実際の生存した日が違っていた場合、家族とトラブルになる可能性もあるので、医師によっては、余命宣告をしない人もいるようです。
資料請求をご希望の方は下記のボタンからお申し込みください。
 スポンサーリンク
スポンサーリンク
余命宣告された場合の家族の対応
余命宣告された場合の家族の対応はどのようにすればいいのでしょうか。
今後の治療方針を検討する
余命宣告された場合、家族は緩和ケアに取り組むことになります。
緩和ケアとは、余命宣告を受けた人の精神的、身体的な苦しみや傷みを少しでもやわらげることです。
がんは現在の日本で最も多い死因となっていますので、がん患者の家族による対応が緩和ケアの代表と言えるでしょう。
余命宣告されて、なんとか延命治療ができないものかと考えたり、治療できると信じたりしてセカンドオピニオンを受けることもあります。
別の医師に異なる視点で診断してもらうことは今の時代ではあたりまえのことで、主治医に失礼と考える必要はありません。
こっそり別の病院を受診するのではなく、これまでの主治医から検査結果データを受け取って新しい医師に見せるようにしましょう。
本人のしたいことをさせる
どんなに小さなことでも、本人のしたいことを極力やらせてあげるのも悔いのない人生をおくるうえで必要なことです。
たとえば、食べたいものや飲みたいもの、会いたい人、行ってみたいところなどがあるでしょう。
本人のこういった願いが叶えられるようにサポートしてあげることが大切です。
食べたいものや会いたい人、行ってみたい場所といった本人のやりたいことを紙に書いてリスト化し、順番にかなえてあげることもいいのではないでしょうか。
リストアップすることで、本人のやりたいことが達成できたかが一目でわかるので、達成感がありますし、幸福感も味わえます。
接する時間を長くする
余命宣告を受けた本人と接する時間を長くすることも大切です。
余命宣告を受けたことで本人は大きな不安をかかえています。
一人きりにしてしまうと、絶望を感じるのは当たり前のことでしょう。
家族などが近くで見守ってあげたり、残りの時間を過ごしたりして思い出話を作ったり、気落ちしている場合はポジティブに接して、本人を前向きにさせ、不安をかなり払拭できるでしょう。
加えて、本人のそばにいてあげれば、非常事態が起きた時でも緊急対応が可能です。
医師にすぐに連絡できますし、本人の気持ちに余裕を持たせることもできます。
保険会社に連絡をする
保険の契約をしているなら、保険会社に連絡して契約の内容を確認しましょう。
余命6カ月以内と宣告された場合、死亡保険金の一部または全額を存命中に受け取ることができるリビングニーズ特約もあります。
生前に保険金を受け取ることができるため、医療費にも充当でき、そのため治療の可能性が広がる場合もあるでしょう。
あるいは、今後の人生を充実させるための資金になるかもしれません。
資料請求をご希望の方は下記のボタンからお申し込みください。

余命宣告された場合の本人の対応
余命宣告された場合の本人の対応はどうすればいいのでしょうか。
今後の希望を伝える
余命宣告を受けた本人としては、医師に今後の治療方針を確認し、意識を失った場合はどのような最期を希望するのかを伝えておきましょう。
病院では、意識がない状態では通常、延命措置を行います。
延命措置を 望まず、「安楽死」という自然な形での最期を希望する人もいるでしょう。
本人が安楽死を希望していたにもかかわらず、家族の誰も知らなかったため延命措置が行われてしまったという事態もあります。
どのような最期を希望するのかを、家族間で十分話し合っておくと安心できるでしょう。
終活を始める
相続や葬儀の準備といった終活を始めるのも本人の対応の1つとなります。
葬儀の準備
自分の葬儀について考えておきます。
葬儀の事前相談は基本的には無料ですので葬儀社などに聞いてみましょう。
複数の葬儀社から見積りをとって、葬儀の形式、規模などから比較検討します。
葬儀社の生前会員に登録しておけば、葬儀費用の割引などの特典が受けられることもありますし、いざという時にスムーズな対応ができます。
臨終を迎えたときでもあわてないように、臨終となった時に連絡したい人のリストを作成しておくのもいいでしょう。
相続の準備
財産の内容を確認し、誰に何を相続させるのかを明確にしておくとトラブル防止になります。
相続財産の目録を作成して、負債があればその金額も示しておくといいでしょう。
遺言書に遺言書の形で残しておくのがおすすめです。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
弁護士、行政書士、税理士などに財産確認を依頼してよいでしょう。
遺言書の作成
遺言書の形で残しておくのがトラブル防止には最適です。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的に利用されます。
「自筆証書遺言」は簡単に作成ができ、費用も発生しませんが、法的要件を満たしていない場合は無効となる恐れがあります。
また、余命宣告を受けるような状態では遺言書を自筆で作成するのは困難な場合が多いでしょう。
法律の専門家である公証人による公正証書なら、確実に遺言を残したい場合や字を書くことができない場合でも対応可能です。
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認がないため、短時間で相続開始以降の遺言内容の遂行ができます。
また、遺言書の原本が公証役場に保管されるので、改ざん、紛失等の心配もありません。
エンディングノートの作成
「エンディングノート」に自分の考えや希望を書いてみるのもいいでしょう。
エンディングノートに記載される内容は以下のとおりです。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 配偶者や子ども・兄弟姉妹・親戚に関する氏名や住所・連絡先
- かかりつけの病院の連絡先
- 延命措置についての希望
- 葬儀に関する希望
- 相続や財産・保険に関する内容および連絡先
- 通帳や印鑑の保管場所
- 家族や友人知人へのメッセージ
エンディングノートには決められた形式などはなく、好きなノートを使ったものでもかまいません。
なるべく早いうちからエンディングノートを書き始め、残された時間を悔いなく過ごすようにしましょう。
なお、エンディングノートには遺言書のような法的拘束力はありません。
挨拶を済ませる
余命宣告を受けたら、家族や知人に挨拶することも考えましょう。
家族や知人に伝えた方がいいのか迷ってしまう場合もあります。
そういう時は、告知を受ける相手の立場になって、伝えた方がいいのかを考えるのがいいでしょう。
対面では伝えづらい場合は、手紙を書いて渡す方法もあります。
家族や知人を悲しませたくない気持ちがあるため、余命を誰かに伝えることは勇気と心構えが求められます。
相手の立場にたって考え、自分らしい方法で後悔のないように連絡をとってみてはいかがでしょうか。
資料請求をご希望の方は下記のボタンからお申し込みください。
 スポンサーリンク
スポンサーリンク
本人に余命を伝えるべき?
本人に余命を伝えると人によっては自暴自棄になってしまうこともあります。
そうして精神に異常をきたしたり、かえって病気が進んでしまったりする場合もあるかもしれません。
そのためにも伝え方には十分注意が必要で、慎重に言葉を選んで伝えるべきでしょう。
突然のことなので、伝えた方がいいのか伝えないほうがいいのか迷ってしまうのは当然です。
しかし、本人が残された時間を大切にして有意義に過ごすためにも伝えた方がいいのではないでしょうか。
自分の余命をどうしても知っておきたいという人もいますし、自分の余命を知っておけば不安もなく残りの人生を送ることができるという人もいるようです。
余命は通常、医師が家族にまず伝えるものです。
そのため、本人に伝えるのは家族の判断ということになります。
余命を伝えるかどうかは家族で十分に話し合ってきめましょう。
資料請求をご希望の方は下記のボタンからお申し込みください。

余命を確認するには
余命を確認するには医師から教えてもらうのではなく、自分の方から、率直に聞いて見るのもいいのではないでしょうか。
医師が患者に余命を伝えることはどうしても慎重になってしまいます。
そのため、患者からの問いかけを、待っている医師もいるようです。
本人が余命を受け止めることができ、余命という情報の目的が今後の生き方を決めていく上で、本当に大切なものだと言える場合には、医師から宣告されるのを待つのではなく、自分の方から、聞いてみてはいかがでしょうか。
医師からの余命に関する情報は、正確なものではなく、あくまでも目安にすぎないことを念頭に置きましょう。
もし、医師が余命に関することを伝えるのを拒むようならば、その理由を尋ねてみることです。
そこで納得できる説明が得られないならば、紹介状を書いてもらい、セカンドオピニオンを訪ねることを検討しましょう。
資料請求をご希望の方は下記のボタンからお申し込みください。
 スポンサーリンク
スポンサーリンク
家族の余命宣告まとめ

ここまで、家族の余命宣告について家族や本人のとるべき対応を中心に解説してきました。
まとめると以下の通りです。
・余命宣告された場合家族は、今後の治療方針を検討したり本人の好きなことをさせたりする。
・余命宣告された場合本人は、今後の希望を伝えたり終活をはじめたりする。
・残された時間を有効に使うためにも本人に余命を伝えるべきである。
・余命を伝える時は、慎重に、しっかりした目的などを伝えるようにする。
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
みんなが選んだ終活では365日24時間葬儀に関するお悩みに対応しています。
葬儀にかかる料金などにも回答しますのでぜひお申し付けください。

都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

田中 大敬(たなか ひろたか)
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査制度 一級 葬祭ディレクター
経歴
業界経歴15年以上。葬儀の現場で数々のお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから著名人や大規模な葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとに数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、特に士業や介護施設関係の領域に明るい。
終活の関連記事
終活

更新日:2022.05.17
葬儀後の遺影はどうするべき?保管方法や処分方法について解説
終活

更新日:2022.05.03
遺影を選ぶとき笑顔の写真は避けるべき?最適な表情、選び方を解説
終活

更新日:2022.05.10
なぜ遺影を仏壇の上に飾ってはいけないのか?飾る場所について紹介
終活

更新日:2022.05.17
浄土真宗の遺影の飾り方は?浄土真宗の祭壇やルールを解説!
終活
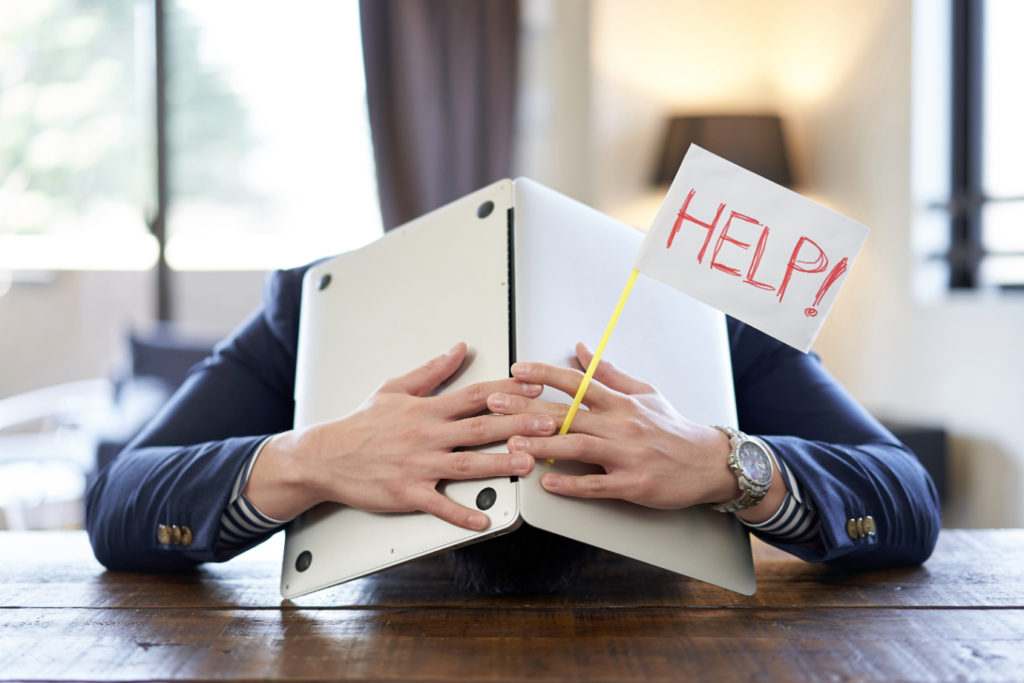
更新日:2024.08.01
遺品整理でよくあるトラブルとは?トラブルの回避法と業者選びを説明
終活

更新日:2025.01.21
認知症の場合の遺言書は有効?判断基準と無効の場合の対処法を説明