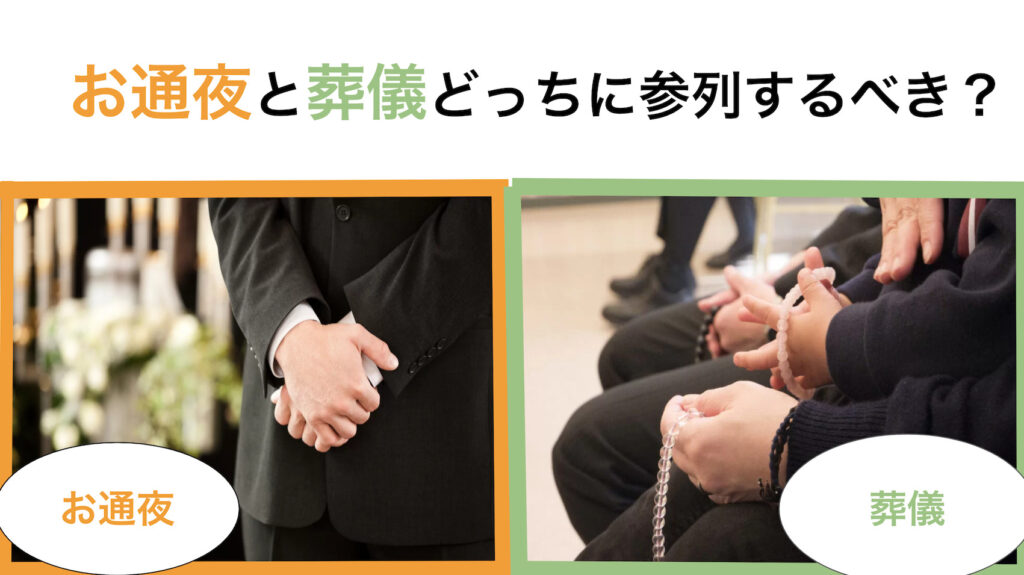お葬式
祖母の訃報に弔電を出す時の文例は?弔電のマナーと合わせて紹介
更新日:2022.11.19 公開日:2021.12.10

記事のポイントを先取り!
- 参列できない時は弔電を出す
- 通夜の前に届くよう手配する
- 弔電では忌み言葉や重ね言葉を使わない
訃報を聞いた際、事情があって葬儀に参列できない場合、お悔やみを伝える手段となるのが弔電です。
しかし弔電にどのようなマナーがあるのか分からない方も多いのではないでしょうか。
祖母の弔電に適した文面や送る際のマナーを知って、適切にお悔やみの気持ちを伝えられるようにしましょう。
今回は、祖母の訃報への弔電の出し方について中心に解説します。
文面の具体例も記載しているので参考にしていただけますと幸いです。
ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
祖母の訃報には弔電を出す?

そもそも祖母の訃報に際して、弔電を出すべきなのかどうか分からないという方も多いのではないでしょうか。
弔電をだすかどうかの判断材料となるように、訃報を受け取った際の対応や弔電についての考え方を解説していきます。
葬儀の参列が最優先
祖母の訃報を受け取った際、第一に考えるべきことは祖母の葬儀へ参列できるかどうかです。
身内が亡くなった場合には、基本的に葬儀に参列するのがマナーとされています。
そのためまずは予定を移動したり、休みにしてもらったりすることでどうにか葬儀への参列ができないか確認してみましょう。
遠方に住んでいる場合は弔電を出す
できるだけ葬儀には参列すべきですが、参列できない場合は弔問するという手段もあります。
最初に葬儀・弔問が可能かどうかを検討しましょう。
しかし遠方に住んでいたり仕事などが多忙であったり、このころ中においてはすぐに弔問するのが難しかったりすることもあります。
そのようなやむを得ない事情がある場合には、弔電をだすことで祖母へのお悔やみの気持ちを伝えるようにします。
すぐには駆け付けられない場合にはまず弔電を送り、後日時間ができた際に直接弔問することをおすすめします。
弔電での祖父母の呼び方

弔電を出すことになった場合、気をつけなければならないのが弔電での呼び方です。
弔電は、基本的に亡くなった祖父母に対してではなく喪主に対して出すものとなります。
そのため自身の祖父母の訃報を受けて弔電を出す時には、喪主の立場に応じて敬称も変化するのです。
以下で故人と喪主の関係性によって、どのように敬称が変化するのか参考にしていただければと思います。
| 故人が喪主の父親 | ご尊父様・お父様・父上様 |
| 故人が喪主の母親 | ご母堂様・お母さま・母上様 |
| 故人が喪主の夫 | ご主人差様・ご主君様 |
| 故人が喪主の妻 | 奥様・奥方様 |
| 故人が喪主の祖父 | ご祖父様・御祖父様 |
| 故人が喪主の祖母 | ご祖母様・御祖母様 |
故人が自分の祖父母であったとしても、上記のように喪主と故人の関係性によって呼び方を変えることを忘れてはいけません。
訃報の連絡を受けて弔電を出す前に、喪主が誰であるのかを確認しておく必要があるため注意しましょう。
しかし、弔電では必ず上記の敬称を使わなければならないという訳でもありません。
上記の敬称を使わず、親しみを込めていつも使っている呼び名を用いて弔電を書くことも増えています。
故人や遺族へ自分の想いが伝わるように、弔電を書くと良いでしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
祖母の弔電の注意点

ここからは祖母への弔電をだす際の注意点について解説していきます。
以下の点に注意して、マナーに則った弔電を送れるようにしましょう。
忌み言葉を避ける
弔事で使用すると縁起が悪いとされている「忌み言葉」は使わないようにしましょう。
忌み言葉とは死や不幸、苦しみなどを連想させるものです。
例えば、直接的な表現にあたる「死去」や「生存中」などといった言葉は避けるようにします。
加えて、四や九も「死」や「苦」を連想させるため、忌み数字といわれています。
またこれらとは別に「重ね言葉」も、弔事で使用することはマナー違反だとされています。
例えば「何度も」や「重ね重ね」「たびたび」のような表現は、「不幸が繰り返す」というイメージが連想されてしまうため、葬儀や告別式の場に相応しくありません。
弔電ではこうした表現は他の言葉に言い換えて、文中で重ね言葉を使用しないようにしましょう。
通夜の前に届くようにする
弔電は基本的に通夜までに届くように手配するのがマナーだとされています。
訃報を聞いて自分が葬儀に行けないということが分かったら、すぐに用意を始めるようにしましょう。
しかし、もし弔電が通夜までに間に合わなくなってしまった場合でも、葬儀・告別式に間に合えば問題ありません。
また弔電の送り先は葬儀が行われる会場宛に、宛名は故人ではなく喪主になるため、注意しましょう。
斎場で葬儀が行われる場合には斎場へ、故人の自宅で葬儀が行われる場合には、自宅宛に弔電を送ります。
弔電を送る前にしっかりと確認し、宛先を間違えないようにしましょう。
祖母の弔電の文例

ここからは、祖母の訃報に際して弔電を送る際の文例をご紹介していきます。
敬称を使うパターンや、生前祖母と関係性が近しかったパターンなど、シチュエーション別にご紹介します。
以下の文例を参考に、自分で弔電の文面を作成していただければと思います。
文例1
ご母堂様の突然のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。
ご遺族の皆様のお悲しみをお察ししますとともに、故人が安らかに永眠されますよう、心よりお祈り申し上げます。
文例2
突然の訃報に接し、驚いております。ご祖母様はいつも優しく私のことを迎えてくださいました。
ご生前の数々の笑顔が、今も思い出として私の胸の中にあります。
心からご冥福をお祈り申し上げます。
文例3
訃報に接し、悲しい思いでいっぱいです。おばあちゃんはいつも笑顔で私のことを愛してくださいました。
遠方のため駆け付けられないことが残念でなりません。
心からおばあちゃんの冥福を祈っております。
天国から私のことを見守っていてください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
孫同士で連名で送る場合

弔電をだす際、孫一同として連名で送る場合もあるでしょう。
そのような場合には、どのように差出人を書けば良いのかを以下で解説していきます。
三人以下
三人以下の場合には、差出人名は並べて名前を書くのがマナーです。
孫同士で連名で差出人名を書く場合には、年齢順で書くようにすると良いでしょう。
また、弔電を送る際には差出人の住所と連絡先も記載することとなります。
三人以下の場合には、全員分の住所と連絡先を書くのが良いでしょう。
住所と連絡先は、遺族側が弔電に対してお礼をする際にも必要となるものですので、省略しないようにしましょう。
四人以上
四人以上になる場合には、差出人欄に全ての人の名前を書くのは難しくなります。
そのため「孫一同」と書くようにしましょう。
また住所と連絡先に関しても、全員分を記載するのは難しいため、代表者一名のみ記載するようにします。
弔電と香典のどちらも送る場合

祖母の訃報を受け、葬儀に行けるのであれば香典を持参して参列するのが良いでしょう。
しかし何らかの理由により葬儀に出席できず、弔電を出すことになった場合、弔電と香典の両方を送りたいということもあるかもしれません。
弔電と香典を両方送ることに問題はありませんが、その送り方には注意が必要です。
ここでは両方送る場合のタイミングについて解説していきます。
弔電が先につくようにする
弔電と香典の両方を送る場合には、弔電が先につくように、葬儀に参列できないことが分かった時点で送る準備をしましょう。
訃報から葬儀まではあまり時間がないことが多いため、できるだけ早く弔電を送る必要があります。
もし告別式までに弔電を送ることが難しい場合には、遺族に対して参列できない旨を伝え、その上で香典を送るようにしましょう。
香典は弔電の後に送る
香典は葬儀に参列する場合には、葬儀に持参して喪主に渡します。
葬儀に行けないのであれば、香典は後から渡すようにしましょう。
葬儀に参列できない時の香典は、基本的に葬儀から1週間後辺りを目安に故人の家に弔問し、遺族に渡すのがマナーとして最良です。
しかし故人の家が遠く、伺うことが難しい場合には郵送で送るという手もあります。
香典を郵送で送る場合には、不祝儀袋に香典を入れ現金書留で送りましょう。
その際、遺族に宛てて書いたお悔やみの手紙を添えるようにします。
便箋は弔事に相応しいシンプルなものを選び、お悔やみの言葉や自身の想いなどを書きましょう。
祖母への香典の相場
香典は自身と故人との関係によって変動するのが一般的です。
ここでは祖母への香典の相場について解説します。
一般的に知人・友人への香典よりも、身内への香典の方が高額になる傾向があります。
また、年齢が若ければ若いほど渡す香典の相場は低くなるのが一般的です。
祖母への香典の場合、20代・30代の方は1万〜3万円が相場だとされています。
これが40代になると相場が高くなり、3万〜5万円になります。
あまりに高額になると喪主や遺族の方が気を遣ってしまうため、相場の範囲内に収めるようにしましょう。
また香典を入れる香典袋は、金額によってデザインも変えるようにします。
香典の中身が1万〜2万円の場合には、水引が藍銀か白黒で7〜10本付いている袋を使いましょう。
中身が3万〜5万円の場合は、水引が藍銀で10本以上付いている袋が最適です。
上記を参考にして、最適な香典袋を用意するようにしましょう。
香典で渡すお札は新札ではなく古いお札を用意します。
これは、新札を用意すると訃報が来ることを事前に予想していたと遺族の方が思ってしまい、不謹慎になってしまうためです。
もし手元に新札しかない時は、新札に折り目を付けるようにしましょう。
ただし、破れていたりボロボロすぎるお札を使うことも避けましょう。
香典の相場と渡し方のマナーを守ることで、遺族の方が不快に思わないようにしましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
祖母の弔電まとめ

ここまで祖母の弔電を出す際のマナーに関する情報や、注意点などを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 祖母の葬儀に参列できない場合には弔電を出す
- 弔電を書く際には忌み言葉を避け、通夜の前に届くように手配する
- 弔電と香典を両方送る場合には弔電を通夜の前に送り、香典は後から渡す
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
監修者

唐沢 淳(からさわ じゅん)
経歴
業界経歴10年以上。大手プロバイダーで終活事業に携わる。葬儀の現場でお葬式を担当し、身寄りのない方の弔いから大人数の葬儀までを経験。お葬式を終えた方々のお困りごとにも数多く寄り添いサポートを行う。終活のこと全般に知見を持ち、ユーザー目線でのサービス構築を目指す。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2022.11.17
日にちが経ってからお悔やみの言葉を伝えるには?文例なども紹介
お葬式

更新日:2025.05.19
葬儀でのお別れの言葉を紹介!弔辞の例文やマナーを解説
お葬式

更新日:2022.11.17
追悼の意味とは?使い方や追悼文を書く際の注意点を解説
お葬式

更新日:2023.11.21
弔辞におけるタブーとは?忌み言葉の言い換え方も紹介