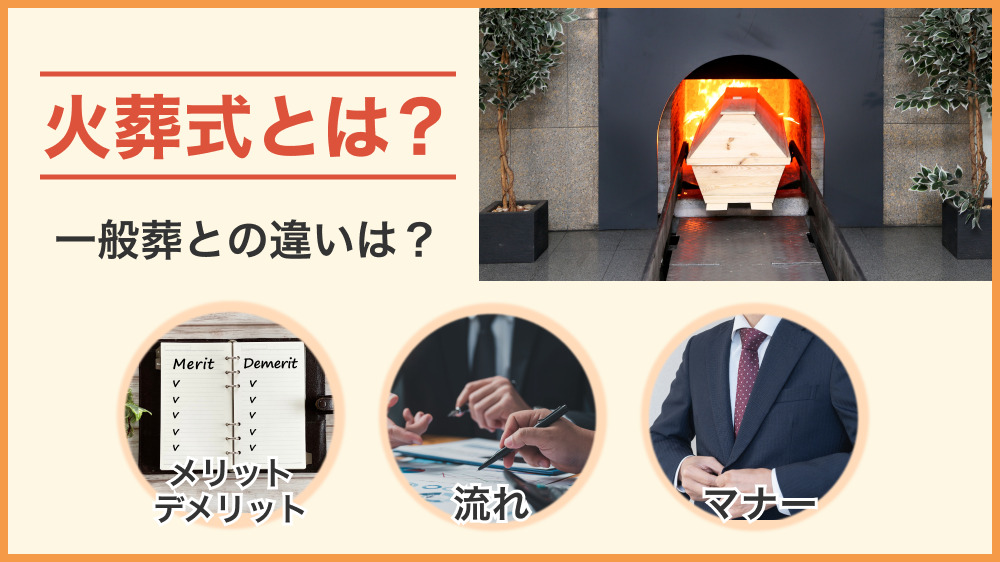お葬式
お通夜の日程の決め方とは|その他葬儀の日程や段取りについても解説
更新日:2024.02.18 公開日:2021.06.18

記事のポイントを先取り!
- 通夜の日程は故人が亡くなった次の日
- 告別式や葬儀はお通夜の次の日に行う
- 火葬場が友引の日に休みの場合があるため注意
身内の方を亡くしてしまい、お葬式を執り行う際、日程をどのように決めていいかわからないという方も多いのではないでしょうか?
何かあったそのときに葬儀の日程や段取りのことで悩んでしまう前に、当記事でしっかり基本情報を抑えておきましょう。
この記事では、葬儀日程の決め方や連絡する相手や連絡方法についてご説明します。
葬儀前から葬儀後までの一般的な流れや段取り、忙しい喪主の手助けができるような知識も記載していますので、最後までぜひご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
- 葬儀の日程の決め方
- 葬儀の日程を決めるポイント
- 葬儀の日程を決める際の注意点
- 葬儀を行ってはいけない日
- 葬儀形式別の日程と流れ
- 亡くなってから葬儀までの日数
- 葬儀日程の連絡について
- 葬儀後の初七日、四十九日の日程はいつ?
- 仏式以外の葬儀・法要の日程
- 葬儀当日をスムーズに進めるためには
- よくある質問
- 葬儀の日程の決め方まとめ
葬儀の日程の決め方
葬儀の日程の決め方は、一般的に故人の亡くなった日を基準に考えます。
法律上や休業日の環境で葬儀ができない日もあるため、下記にかいてあることを覚えておきましょう。
通夜の日程
通夜は故人が亡くなった次の日に行います。
ほとんどのケースでは、夕方から夜にかけて行います。
一般的には午後6時くらいに開始します。
地域によって習わしは違いますが、通夜のあとは通夜振る舞いの席を設けます。
葬儀・告別式の日程
告別式や葬儀は通夜の次の日に行われることが一般的です。
開始時刻は、午前中か午後の早い時間などの日中が多いです。
火葬式の日程
お葬式や告別式は通常、火葬と同じ日に執り行われることが一般的です。
具体的には、法律上、故人が亡くなってから24時間経過した後に火葬を行うよう規定されています。故人の死亡日には火葬ができないため、多くの場合、葬儀や告別式と同時に火葬が行われることがよくあります。
葬儀の後に行われる「後火葬」、逆に葬儀の前に行われる「前火葬」には地域によって異なる規定があるため、細心の注意が必要です。
前火葬の場合、出棺後に火葬を行い、その後に遺骨を祭壇に安置して葬儀を行います。
年末年始の場合
年末年始に故人が亡くなった場合、留意すべきは火葬場の休業日です。
通常、火葬場は年始(1月1日~1月3日)に休業することが一般的です。
このため、葬儀も火葬場の営業に合わせてお正月休み明けに執り行われる傾向があります。
また、休み明けの葬儀や火葬は非常に混雑することが予想されます。
そのため葬儀までの期間においては、安置施設の利用など適切な対応を検討することが重要です。
葬儀の日程を決めるポイント
日程は葬儀を行うのを避ける日があるので、必ずしも前述したような日程にはなりません。
ここでは日程を決める上で確認すべきことを紹介します。
式場・火葬場の空き状況
まず確認すべきは火葬場の予約です。
特に東京を中心とした都市部では、予約が埋まっていることが多く、斎場の予約はしたけど、翌日の火葬の予約ができないということが起きてしまいます。
また、年末年始や友引は休館であるが多いため、火葬場へ連絡して日程の調整をしましょう。
火葬式や直葬についての詳しい解説はこちらをご覧ください。
遺族や参列者の都合
家族や親族に参列していただく必要があれば、それぞれの都合を確認しましょう。
遠方から参列される方もいる場合は、週末に葬儀の日程を合わせることもあります。
事前に確認しておくとよいでしょう。
菩提寺や僧侶のスケジュール
菩提寺があれば菩提寺に連絡をして僧侶のスケジュールを確認しましょう。
僧侶にも予定があるため、必ずその日に来ていただけるとは限りません。
どうしても都合がつかない場合は、同じ宗派の僧侶を紹介していただけるか確認しましょう。
菩提寺があるにもかかわらず、別の宗派で葬儀を行わないようにしましょう。
宗派や戒名の関係から、納骨をしていただけないことがあります。
あらかじめ家族、または親族に確認しておきましょう。
葬儀における僧侶の役割について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
一日葬の場合、昼間に集まれるか確認
告別式と火葬のみの一日葬の場合、平日の昼間に葬儀を行うため、参列者の都合が悪い可能性もあります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀の日程を決める際の注意点
葬儀の手配をする際には、日程や流れなどに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、葬儀の日程を決める際の注意点について説明していきます。
火葬は24時間後にしかできない
あまり知られていませんが、故人がなくなってから24時間経過していないと火葬をすることができません。
これは「墓地、埋葬等に関する法律」により、死後24時間以内の火葬・埋葬が禁止されているためです。
しかし、例外もあります。
下記の場合は24時間以内に火葬・埋葬が可能です。
- 妊娠7カ月に満たない死産のとき
- 感染症による死亡のとき
火葬場の休みに重なってしまったり、予約が埋まっている事もあるので、葬儀の手配をする際には、まず、火葬場の予約を優先して行う必要があります。
火葬について更に詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。
葬儀の場所と時間に気を付ける
葬儀を行う際は、交通手段や時間帯に無理のないよう、十分に気を配るようにします。
火葬の時間が早すぎたり遅すぎたりすると、告別式の時間帯が早朝や夜遅い時間になってしまいます。
すると遠方の参列者は、時間が合わないなどの問題が生じてしまいます。
また、葬儀を行う場所のアクセス方法も重要です。
葬儀場の場所が駅から離れていたり、バスの本数が少なかったりすると、参列者が葬儀の時間に間に合わないという可能性もあります。
葬儀に来る遺族や、参列者に無理のない場所や時間を設定するようにしましょう。
参列する親族と相談する
葬儀の日程を決める時には、遺族だけでなく参列者ともよく相談するようにします。
遺族や参列者の日程が合わず、参列できない方が多いと、葬儀後に多くの弔問客の対応に追われるということもあります。
葬儀の日程は、あらかじめ、親しい友人や知人にも相談をして、温かく故人を見送る準備を進めるようにしましょう。
地域による葬儀日程の違い
葬儀の日程は地域によって異なる場合があります。
通夜は、一般的に故人が亡くなった日の翌日に行われますが、地域によっては亡くなった当日に行われる事もあります。
火葬についても、一般的に多いのは葬儀・告別式の後ですが、葬儀・告別式の前に火葬を行う地域も少なくありません。
六曜に関しても、地域によって捉え方の違いがありますので、周りの人にあらかじめ話を聞いておくなどして、「友引」「仏滅」の日は特に注意しておきましょう。
葬儀までの日数によって安置費用が異なる
葬儀まで期間が空く場合、葬儀の日まで遺体を保管するための費用が発生します。
安置施設利用料やドライアイス代が含まれています。
また、長期間保存する場合はエンバーミングという特別な処置が施されるため、さらに費用が発生することに注意しましょう。
葬儀を行ってはいけない日
葬儀日程を検討するにあたって、行ってはいけない日にちはあるのでしょうか。
友引
六曜の「友引(ともびき)」を避ける風習があることはよく知られているかと思います。
「友を引く」、つまり「友人を道連れにする」とのイメージが現代まで定着しているため、一般的に「友引」に葬儀を執り行うことがほとんどありません。
本来仏教と六曜には何の因果関係もないため、「友引」に葬儀を執り行ってはいけないというルールは存在しません。
しかし、火葬場が「友引」の日をお休みにしていることがあるため、物理的に葬儀を執り行うことができないこともあるので事前に火葬上のチェックをしておきましょう。
仏滅
仏滅とは物滅とも呼ばれていた日であり、すべての物が滅びる凶日だとされています。
すべての物が滅びる一方、滅びたあとには新しい物事が始まる前段階という考え方も含まれています。
現在の文字となる仏滅であっても、仏が滅びるというあまり字面の良い言葉ではないため、お祝いごとなどを避ける方もいる六曜です。
仏滅に葬儀を行ってもいい
友引でも葬儀を執り行って良いとされているように、そもそも六曜を気にかける必要はないため仏滅に葬儀を執り行ったとしても問題ありません。
また、友引と違い仏滅だからと火葬場が休みになりがちでもないので、葬儀が執り行いにくいなどということもないでしょう。
上述した通り、仏滅には新たな出来事が始まる前の段階でもあります。
そのため、葬儀では故人との別れを終わらせて新しい生活を生きると考えて、むしろ仏滅に行う方もいるようです。
仏滅の葬儀に関しては、以下の記事で詳しく解説があります。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀形式別の日程と流れ

一般的には故人が亡くなった翌日にお通夜を執り行います。
そしてお通夜の翌日に葬儀式・告別式を執り行い、火葬へと進行していきます。
お通夜から火葬までを二日間の日程で行うのが一般的ではありますが、葬儀のスタイルによっては一日で行うこともあります。
さまざまな日程の組み方を検討しましょう。
具体例な葬儀の日程、タイムスケジュールをそれぞれの葬儀スタイル別に紹介します。
一般葬の日程
故人が亡くなった翌日にお通夜を執り行い、その翌日に葬儀・告別式へと進行する一般的な葬儀のスタイルです。
家族・親族だけでなく、親しい友人や仕事の同僚、近所に住まいの方などに葬儀の案内をします。
お通夜
故人を偲ぶために参列者を招いて、最後の夜を過ごし、遺族と食事をしながら故人を偲ぶ儀式です。
一般的にお通夜は亡くなった日の翌日の18時頃から行われます。
葬儀・告別式
お通夜が執り行われた翌日に、葬儀・告別式を10時頃から開始するのが一般的です。
一般葬の場合、参列するのはどちらか片日でも問題ありません。
最近では時間的な問題から、夕方から行われるお通夜の方に参列する方が増えている傾向にあります。
火葬・収骨
葬儀を終えた後、火葬場が別の施設であれば移動し、火葬・収骨へと続きます。
故人の体格や年齢にもよりますが、焼くだけでなく、冷めるまでの冷却時間もあるため、収骨までの時間を含めると1時間から2時間程度の時間がかかります。
一般的に火葬の間の時間は別室にて食事を取ります。
精進落とし
精進落としとはかつては忌明けの食事のことでした。
しかし、現代では精進落としが早まる傾向にあり、火葬を終えたあとに執り行なわれるのがもっとも一般的となりました。
地域によっては火葬中に精進落としを執り行うこともあります。
家族葬の日程
家族葬とは、家族・親族を中心に親しい友人のみで執り行う葬儀のスタイルです。
基本的な葬儀の流れは一般葬と同様です。
家族・親族と親しい友人のみであるため、比較的自由のきく葬儀となり、またその分故人を思う方々の想いを葬儀に反映しやすいでしょう。
家族葬の場合も一般葬と同じく、お通夜、葬儀・告別式、火葬・収骨、精進落としの順に行います。
一日葬の日程
一日葬とは、お通夜を行わずに故人が亡くなった翌日に葬儀・告別式を行うスタイルを指します。
お通夜を省くことでその分費用を抑えることができ、また遺族の負担も減らすことができます。
一日葬の場合はお通夜は行いませんが、他の部分の流れは一般葬と変わらず、葬儀・告別式、火葬・収骨、精進落としの順で行います。
また、一日葬の場合精進落としを省略する場合もあります。
亡くなってから葬儀までの日数
葬儀までの日数は、選択する葬儀の形態によっても異なります。
鎌倉新書の2019年の調査によると、平均して故人が亡くなってから葬儀が行われるまでの日数は約3.135日です。
斎場や火葬場の都合、僧侶の予定などの要因によっても、実際の執り行いはその前後に変動することがあります。
気温の違いも考慮され、寒冷な10月から3月にかけては葬儀に通常3日以上の期間がかかることがあります。
逆に、温暖な4月から9月では、2日以内に葬儀が行われることがよくあります。
これは、夏季の高温により遺体が劣化しやすく、そのために素早い葬儀が求められるからです。
葬儀日数については以下の記事で詳しく解説していますので、こちらをご参考ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀日程の連絡について

葬儀の日程について、どのタイミングで連絡していいのかわからない方も多いと思います。
ここでは葬儀日程を連絡するタイミングについて解説します。
親族
故人が亡くなったらまずは親族に連絡しましょう。
親族の皆さんの予定を確認し、葬儀の日程が決まったら一番に連絡するのが望ましいです。
友人・仕事関係
親族の方に連絡した後、親しい友人や仕事関係の方に連絡しましょう。
連絡方法は電話・メールでもかまいません。
特に故人と親しかった方にはなるべく早くお知らせすることが大切です。
連絡が遅かったことでトラブルに発展することがありますので、故人と親しかった方へは、亡くなってすぐに連絡するほうがいいでしょう。
葬儀後の初七日、四十九日の日程はいつ?

葬儀を終えたあとは、「初七日(しょなのか)」「四十九日(しじゅうくにち)」を執り行います。
仏教において、故人の魂が成仏せずにこの世にとどまっている期間を「中陰(ちゅういん)」といい、これが49日間とされています。
この中陰の期間中、故人は7日ごとに閻魔大王から裁きをうけ、7回目の49日目のお裁きによって、行先が決まるとされています。
初七日
故人が亡くなってから7日目に執り行うのが「初七日」です。
この日は故人が三途の川へ到着する日とされています。
また閻魔大王の裁きによって川の流れの速さが決まる日とされており、緩流で渡れるように供養します。
最近では「繰り上げ初七日法要」といって、葬儀の当日に執り行うことが一般的になってきました。
四十九日
故人が亡くなってから49日目に執り行うのが「四十九日」です。
故人がこの日、閻魔大王の裁きによってあの世への行先が決まるとされているため、極楽浄土へいけるように供養をします。
本来であれば忌日(きび)に執り行うのがよいですが、参列者の都合も考慮して、最近では週末に行うことが多いようです。
法要に関してさらに詳しく知るには、ぜひ以下の記事をご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
仏式以外の葬儀・法要の日程
葬儀や法要の日程は、仏教以外ではどうなっているのでしょうか。
キリスト教
キリスト教のカトリックの場合、古代ローマの風習を引継ぎ、3日、7日、30日、そしてその年の故人の命日に教会で追悼ミサを行います。
場合によっては、葬儀式場などを借りて行うこともあります。
プロテスタントの場合は、教会などで記念式典を行います。
しかし、地域性もあるので、教会や葬儀社に確認した方がいいでしょう。
神式
神道では、故人の死後、十日おきに十日祭や二十日祭、霊祭が行われます。
しかし、仏教に合わせて、十日祭は仏教の初七日に、五十日祭は仏教の四十九日に行われることも多くなってきました。
また、五十日祭、百日祭、一年祭の時に、祖霊舎(それいしゃ)という仏教の仏壇のようなものを設けます。
祖霊舎に霊璽(れいじ)を祀って、故人の霊を先祖の霊とする合祀祭が行われます。
都市部を中心にお墓の区画も小さくなってきたため、最近は、お墓の前で一年祭などを行わずに葬儀場で行われることが多くなってきました。
神道の儀式は、もともと人々の生活に根付いて行われていた祭典が、年月を経て変化したものなので、厳格なルールはありません。
そのため、地方によって作法は異なる場合があります。
作法に迷った時は、まずは、地域の葬儀社に確認するのが一番です。
スポンサーリンク葬儀当日をスムーズに進めるためには
葬儀当日の忙しさを少しでも軽減させるためどうするべきでしょうか。
ここでは葬儀をスムーズに進めるためにどうするべきかを解説します。
葬儀費用を確認しておく
葬儀費用について予算を相談しておきましょう。
一般葬の平均は約200万円となっていますが、家族葬、一日葬など、葬儀形式を変えることで費用は抑えることができます。
予算を把握し、これによって参列者の人数や棺、祭壇などに使用できる費用を確認しましょう。
葬儀の費用に関してさらに知るには、以下の記事をクリック!
葬儀費用の平均相場|内訳や葬儀形式別にかかる費用、費用負担を抑える方法について
参列者の人数を確認しておく
故人が亡くなる前に、誰に参列してほしいかを確認しておきましょう。
また全体として何人参列するかを把握しておきましょう。
葬儀社を決めておく
いざというときに慌てないためにも、葬儀社を事前に決めておくことはとても重要です。
予算や火葬場などを事前に決めておくことが出来れば、当日の喪主、遺族の負担を軽減させることができます。
葬儀社の選び方に関して詳しく知りたい方は、こちらをクリック!
葬儀スタイルを相談しておく
葬儀のスタイルは様々ですが、事前に故人の意向を聞いておくことが出来れば、故人にとっても、残された遺族にとっても、葬儀当日は納得のいった良い葬儀になることでしょう。
事前に相談しておくといいでしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
よくある質問
葬儀の日程についてのよくある質問にお答えします。
Q:もし今日亡くなったら葬儀はいつ?
一般的に、故人の死亡日を基準として翌日が通夜、翌々日が葬儀を執り行う日とされます。
とはいえ、基本的に死は突然訪れるものであり、親族や火葬場、葬儀屋などの都合がつくとも限りません。
可能であれば翌々日に葬儀ができるよう動くのが望ましいですが、最低限の人物が参列できるように予定を組むのが良いでしょう。
Q:葬儀の日程の決め方は?
葬儀の日程を考えるとき、さまざまな要因が関わってきます。
親族・火葬場・葬儀屋など、関係各所の日程をすぐに確認し、すぐにでも日程を考えるようにしましょう。
Q:告別式は亡くなってから何日後にやるの?
告別式は故人との別れを告げる儀式ですが、日本では多くのケースで葬儀とともに行います。
そのため、基本的には死亡日を基準として翌々日が告別式の予定日です。
菩提寺とスケジュールが合わない場合は?
葬儀や法要は、菩提寺の僧侶といった宗教者に連絡し、式を執り行っていただくようお願いします。
とは言え、僧侶も、他の予定と重なることがあり、いつでも大丈夫というわけにはいきません。
僧侶のスケジュールを確認したうえで葬儀や法要に日程を決めるようにしましょう。
そのためにも、極力早めに僧侶のスケジュールをおさえるようにします。
あいにく僧侶のスケジュールが空いていない場合は、希望日から1日や2日程度前後しても問題ありません。
それでもだめな場合は、他の同宗派の寺院の僧侶を紹介してもらうのも一つの方法です。
通夜・葬儀におすすめの曜日は?
通夜や葬儀の日程は、遺族や親族などの身内や、参列者が多く集まれる日がいいでしょう。そのため、週末や祝日に行うのがおすすめです。
遠くからの参列者が大勢の場合は、葬儀当日までに集まることができるように、日程を考慮する必要もあるでしょう。
夜中に亡くなった場合その日に通夜は可能ですか?
基本的には一日開けてから通夜をしますが、夜中や早朝に亡くなった場合に限って、前倒しが可能です。
ただし、急なため参列できない方が出てきます。
焦らずにまず周りにご相談してください。
葬儀の日程の決め方まとめ

ここまで葬儀日程の決め方や、葬儀スタイルごとの流れを中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。
- 一般的には故人が亡くなった翌日にお通夜を行う
- 家族や親族の都合・式場の空き状況など確認して日程を決める
- 日程の連絡はまず親族に連絡し、その後参列者に連絡する
- 葬儀後の法要は初七日、四十九日法要
今回は以上の項目に沿って解説しました。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2022.11.21
町内会の回覧板で訃報のお知らせをするには?文例や注意点を紹介!
お葬式

更新日:2024.03.30
離婚した父の葬儀で喪主は誰がやる?参列の可否や香典の扱いについても解説
お葬式

更新日:2022.11.18
なぜご遺体の手を組む必要があるの?手を組む理由や注意点も紹介
お葬式

更新日:2022.11.18
会葬御礼は郵送した方が良い?弔問客や代理参列者の対応も説明
お葬式

更新日:2022.11.21
供花を頂いたらお礼はするべき?お礼状の書き方や例文も紹介
お葬式

更新日:2022.11.17
枕飾りのご飯(枕飯)とは?いつまでお供えすればいいの?