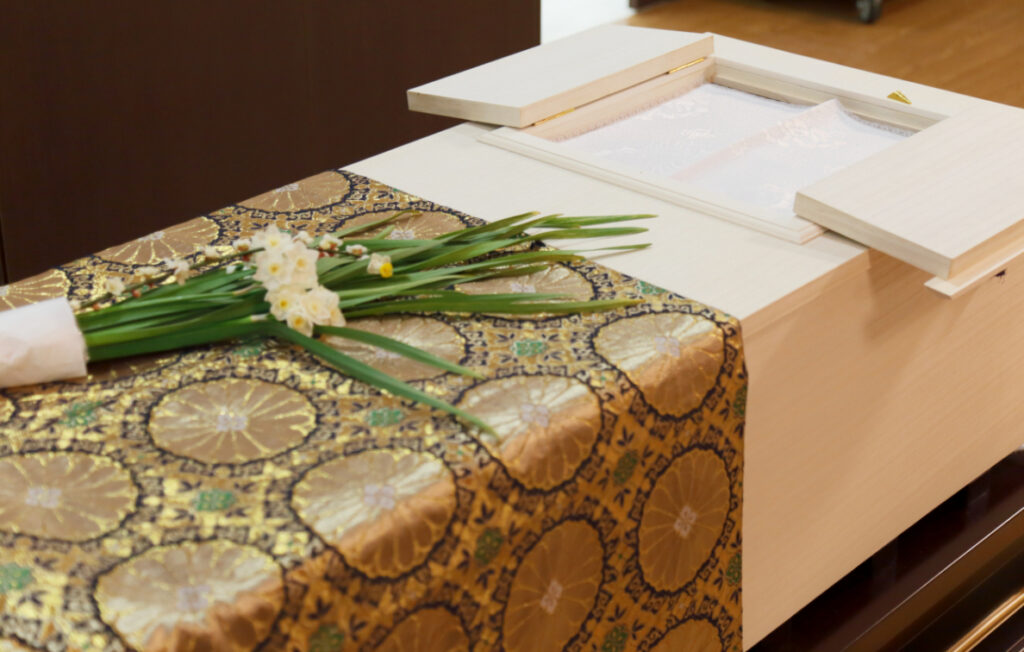お葬式
【葬儀の流れ】ご臨終〜火葬
更新日:2024.04.21 公開日:2021.12.31
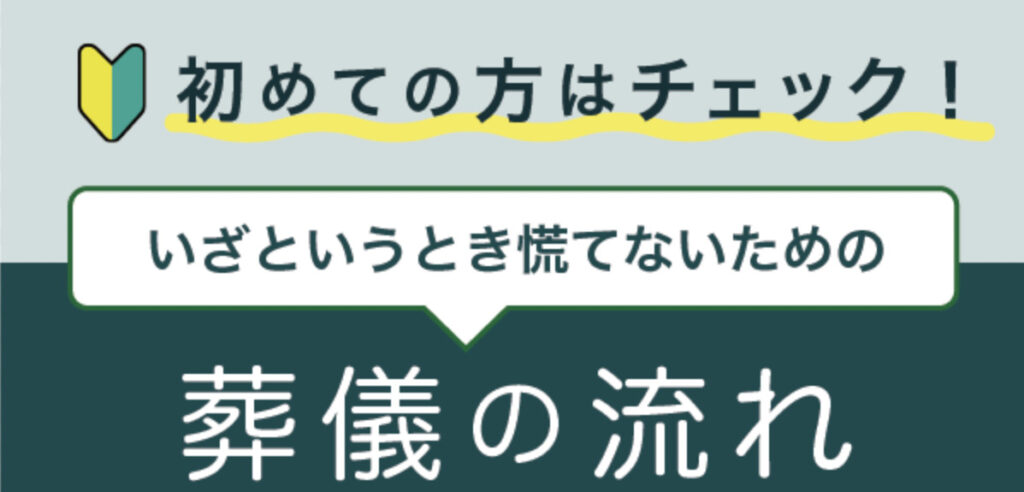
記事のポイントを先取り!
- 死亡宣告を受けたら必要書類を作成してもらい、葬儀社へ連絡
- お葬式の流れは1日目に通夜、2日目に葬儀・告別式と火葬
身内が唐突に亡くなった際、まず何をすべきなのかをご存知ですか?
いざというときのために、ご臨終から火葬までの流れや注意すべきポイントを知っておきましょう。
この記事ではお葬式の流れについてわかりやすく解説します。
お葬式で必要となる準備や、役所で取得する書類についてもこの機会に覚えておきましょう。
コロナ禍で注目される葬儀スタイルについても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
ご臨終

ご臨終に際しての対応や流れについてお伝えします。
病院で亡くなった場合、ご自宅で亡くなった場合をそれぞれご説明しますので参考になさってください。
<お急ぎの方はこちら>
病院で亡くなった場合
病院によって告知の方法は異なりますが、医師から死亡宣告(ご臨終)が告げられます。
死亡の告知後に病院から死亡診断書を作成してもらい受け取ります。
死亡診断書の作成には3000~5000円の費用がかかります。
死亡診断書とは、死亡届を役所に提出する際に必要な書類です。
役所で死亡届と火葬許可証申請書を記入し、死亡診断書とともに役所へ提出すると火葬許可証が発行されます。
火葬場へ行くときに火葬許可証を忘れずに持参しましょう。
死亡診断書の提出は葬儀社の方が代理で行ってくれることが多いようです。
死亡診断書は、故人が亡くなってから7日以内に提出することが義務付けられています。
死亡診断書を受け取る前に、エンゼルケアを行う場合があります。
エンゼルケアとは、故人を納棺する前に行われる遺体処置全般のことです。
故人の体を清める湯灌(ゆかん)・着替え・死化粧を主に行います。
エンゼルケアは基本的に葬儀社が主体となって行いますが、看護師が湯灌の代わりにアルコールで体を清拭する場合もあります。
自宅で亡くなった場合
自宅で亡くなった場合、病気の療養中だったのか、事故や自死の突然死だったのかで対応が異なります。
病気の療養中だった場合
病気の療養中だった場合は、亡くなった後にかかりつけの医師を呼びます。
医師にきちんと確認してもらい、死亡宣告を受けるまでは正式に死亡と認められません。
かかりつけの医師がいない場合は、救急車を呼んで病院へ搬送してもらう形となります。
死亡宣告後はかかりつけの医師から死亡診断書を作成してもらいます。
病気以外で亡くなった場合
事故や自死などで急に亡くなられた場合です。
この場合は遺体を移動せず、すぐに警察へ連絡しなくてはなりません。
警察とともに検視官が同行し、死因を調べることになります。
東京と横浜市の場合は監察医が同行します。
検視を受けた後は警察から死体検案書が提出されます。
死体検案書は死亡診断書と同様の公的証明力があるため大切に保管しましょう。
火葬や埋葬時にも必要な書類となります。
ご臨終の流れに関しては下記コラムでも掲載しておりますので是非ご覧ください
安置

特に病院で亡くなられた場合、一旦は霊安室に移されますが、早急に安置所を決める必要があります。
一般的には故人の自宅か葬儀社の指定した場所へ移動させることが多いようです。
自宅に安置する場合は、仏壇のある部屋へ布団を敷いて安置します。
故人は北枕で安置しますが、間取り的に難しい場合は西枕でも問題ありません。
故人の枕元には枕飾りを置き、僧侶へ枕経を依頼する場合もあります。
自宅にご遺体を安置するメリットは、面会時間に制限がない点です。
遺族や弔問客が故人と最期の時をゆっくりと過ごせます。
ただし、ご遺体が損傷しないように温度調節などに気を使う必要があります。
アパートやマンションにお住まいの方は、大家さんへの事前報告も忘れないでください。
葬儀社が用意した安置室は衛生保全面が安心ですが、面会時間に制限があったり付き添いの方の宿泊は別途料金がかかる場合もあります。
葬儀社の安置室の利用料は、1日5000~3万円前後が相場です。
都市部では火葬場の不足で葬儀がなかなか行えないことが問題となっています。近年は遺体の安置に特化した遺体ホテルもあります。
安置後は火葬場へ移送してくれたり、そのまま直葬や家族葬に対応しているなど様々なプランがあるようです。
1日1万~2万円前後で利用できるようですが、日数がかかればその分出費もかさむ点は留意しましょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
葬儀社への連絡

親族や菩提寺に連絡する前に、葬儀の日程や流れを決定しなければなりません。
葬儀社への連絡は故人が亡くなったあとなるべく早めに行いましょう。
火葬場や斎場の空き具合を確認したら親族と菩提寺へ連絡します。
近しい親族へは葬儀日程が決まっていなくても一報を入れるのがマナーです。
日程が決まり次第、改めて連絡する旨を伝えれば問題ありません。
日本では、故人の死亡が確認されてから24時間以上たたないと火葬ができません。
菩提寺と斎場・火葬場との日程調整ができ次第、親族のほか会社への忌引き連絡をします。
町内会で回覧を回す場合は自治会への連絡も忘れずにしましょう。
葬儀社との打ち合わせでは供花や香典返しの手配・祭壇のグレードなどの詳細を決めていきます。
遺族は僧侶へ渡すお布施の準備なども並行して行いましょう。
<葬儀社をお探しの方はこちらから>
納棺

納棺は故人のご遺体を棺に納める儀式です。
エンゼルケアが済んでいるご遺体を棺に納め、副葬品を入れます。
副葬品として棺に納める際、入れても良いものと悪いものがあるため注意が必要です。
【副葬品としてOKな品物】
- 手紙・花・故人の写った写真
- 洋服
- お菓子
【副葬品としてNGな品物】
- 貴金属類・携帯電話・入れ歯・眼鏡・杖などの不燃物
- 水分の多い食品・飲料
- ライターやスプレーなど爆発の危険のあるもの
可燃物でもぬいぐるみやは燃え残る可能性があるため葬儀社へ確認しましょう。
生きている人の写真やお金なども納められません。
貴金属類は棺には入れられませんが、骨壺ならOKな場合もあるようです。
果物や飲料など水分の多いものは燃焼の妨げになるためNGです。
革製品やゴム製品を入れると融解し、収骨の際に支障をきたすことがありますので入れないようにしましょう。
納棺は通夜の開始時間の3~4時間前に行われるのが一般的です。
納棺のあとに通夜を行う流れになるため、納棺時は喪服を着用していた方が良いでしょう。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
お通夜

お通夜とは葬儀・告別式の前夜に、親族や故人と親しかった人たちに参列してもらう儀式です。
お通夜は本来、夜通しロウソクの灯と線香を絶やさずに故人を見守る儀式でした。
近年は夜通しの見守りをせずに2~3時間の短時間で終わらせる半通夜が主流です。
通夜には仮通夜と本通夜」があります。
仮通夜とは親族のみで故人と静かに夜を過ごすことをいい、宗教儀式は行いません。
本通夜とは一般的なお通夜を指します。
一般的なお通夜の流れは以下のようになります。
お通夜は夕方の18時~19時頃に行われるため、会社帰りに参列する方も多くいらっしゃいます。
一般会葬者のほとんどが葬儀・告別式ではなくお通夜に参列します。
受付は通夜の始まる時間の30分~1時間前から始められるよう準備します。
焼香は故人と近しい間柄の順番で行うため、最初に喪主が焼香をしてそのあと遺族・親族へと続きます。
儀式が終わると喪主から参列者へ向けての挨拶をします。
通夜に参列してもらったお礼と翌日の葬儀・告別式の案内をします。
通夜振る舞いがある場合は会場のお知らせもしましょう。
通夜振る舞いとは、通夜の儀式が終わった後に参列者や僧侶を交えて行う会食のことです。
スポンサーリンク告別式・葬式

通夜の翌日に行うのが告別式・葬式です。
本来は、読経など人の死を弔うために行われる儀式を「葬式」、友人・知人が故人に最期のお別れをする儀式を「告別式」といいます。
現代ではこの2つを一連の流れで行うため、あえて区切らないのが一般的です。
告別式・葬式の流れは通夜とほとんど同様ですが、以下の通りになります。
- 受付
- 僧侶の読経
- 弔辞・弔電の紹介
- 焼香
- お別れの儀
- 出棺
僧侶へ渡すお布施は、僧侶が斎場に来られて挨拶するときや読経後に渡すのが一般的です。
いつ渡すべきかという厳密な決まりはありませんので、わからなければ僧侶へ直接お伺いしても問題ありません。
僧侶が通夜振る舞いや精進落としに参加しない場合は御膳料を1万円ほど包みます。
また、交通費として御車代も5000~1万円が必要です。
読経のお布施とは別々に包み、切手盆にのせて重ねて渡すのがマナーです。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
出棺

告別式・葬式が終わると故人の出棺となります。
出棺の前には棺の中にお花を供える別れ花や、一般会葬者が副葬品を入れるお別れの儀を行います。
別れ花は故人と縁の深い間柄の人から順に供えていきましょう。
棺のふたを閉めた後は釘打ちを行います。
釘打ちには、「遺族が故人の死を受け入れる」「死者のよみがえりを防ぐ」などの意味が込められています。
葬儀場のスタッフが棺の四隅に途中まで釘を打ち込んでおき、遺族が小石や小槌を使って2回で打ち込みます。
葬儀場によってはスタッフが全部釘打ちをしたり、1か所だけを遺族が釘打ちする場合もあります。
近年は釘打ちの儀式自体を行わない斎場が増えているようです。
スポンサーリンク火葬

出棺後は親族のみで火葬場へ向かいます。
このとき、死亡届を提出したときに受理した火葬許可証を忘れずに持参してください。
火葬許可証のほかに位牌と遺影も持参しましょう。
故人が火葬されると職員が火葬許可証に印鑑を押印します。
押印した火葬許可証が埋葬許可証となり、お墓や納骨堂へ納めるときに必要となりますので大切に保管します。
火葬の直前には僧侶に読経してもらい、親族が焼香する「納めの式」が行われます。
火葬が終了するまでに1~2時間かかるため、控室でお茶やお茶菓子を用意して収骨までの時間を過ごします。
葬儀社によっては火葬の間に精進落としを行う場合もあるようです。
収骨の案内がきたら火葬された遺骨を骨壺に納めますが、この儀式をお骨上げ(おこつあげ)といいます。
2人1組となり、長い箸を使って同時に骨壺へ納めていきます。
みんなが選んだお葬式の電話相談
みんなが選んだお葬式では葬儀社、葬儀場選びのご相談に対応しております 他にも、葬儀を行う上での費用、お布施にかかる費用など葬儀にかかわること全般に対応しております。 なにかご不明な点がございましたら以下のボタンから遠慮なくお申し付けください。24時間365日無料相談
0120-33-3737
電話をかける
手配いたします
ご危篤・ご逝去で
お急ぎの方はこちら
厳選して無料でご案内いたします
精進落とし・初七日法要

初七日法要とは故人が亡くなってから四十九日法要まで、7日ごとに行われる追善供養のことです。
本来であれば火葬が終わると遺骨・位牌を自宅に安置し、7日後に再び親族が集まって初七日法要が執り行われます。
しかし、近年は火葬が終わった後に葬儀場へ戻り、初七日法要を行う繰り上げ法要が一般的です。
告別式後に初七日法要の読経をすることもあり、これを繰り込み法要といいます。
通夜・葬儀で親族が集まったタイミングで一緒に行われることが多くなってきました。
精進落としとは、僧侶や参列者に感謝の気持ちを込めて振舞う会食のことです。
会食は葬儀会館の別室に用意されるのが一般的です。
昔は身内が亡くなったあと49日まで肉や魚の食事を絶つ慣習がありました。
もともとは、49日目以降に元の食生活に戻ることを精進落としと呼んでいました。
葬儀の後に行われる精進落としでは懐石料理などが振舞われることが多いようです。
通夜振る舞いでは大皿に置かれた料理が並びますが、精進落としでは個別に御膳が振舞われます。
葬儀の流れまとめ

ここまで、お葬式の流れについての情報や、コロナ禍でおすすめの葬儀スタイルの詳細を中心にお伝えしました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りになります。
- 病気療養中だった場合は死亡診断書、事故死等の場合は死亡検案書を作成してもらう
- 故人の逝去後はなるべく早く葬儀社へ連絡し、安置場所の決定等を行う
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
スポンサーリンク都道府県一覧から葬儀場を探す
こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。

こちらでご希望のエリアから葬儀場を検索できます。
お葬式の関連記事
お葬式

更新日:2022.11.21
町内会の回覧板で訃報のお知らせをするには?文例や注意点を紹介!
お葬式

更新日:2024.03.30
離婚した父の葬儀で喪主は誰がやる?参列の可否や香典の扱いについても解説
お葬式

更新日:2022.11.18
なぜご遺体の手を組む必要があるの?手を組む理由や注意点も紹介
お葬式

更新日:2022.11.18
会葬御礼は郵送した方が良い?弔問客や代理参列者の対応も説明
お葬式

更新日:2022.11.21
供花を頂いたらお礼はするべき?お礼状の書き方や例文も紹介
お葬式

更新日:2022.11.17
枕飾りのご飯(枕飯)とは?いつまでお供えすればいいの?